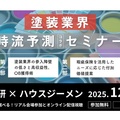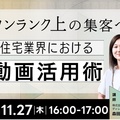木造住宅の耐震化を推進し、組合員1100社を超える団体、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協、東京都新宿区)は1月16日、東京国際フォーラムで「2014年度第16回全国大会」を開催。全国から480人超が参加した。

大会の冒頭で、小野秀男理事長が登壇。「昨年末に出された首都直下型地震の被害想定では、死亡者が2万3000人、61万棟が倒壊、発生確率は30年以内に70%と言われている。東日本大震災でも、2万人近い人が死亡した。一たび地震が起きれば家族が亡くなることは明らか。今こそ私たちが、地震による死者を減らすために行動すべき。車のシートベルトが義務であるように、住宅の耐震診断も義務でなければならない。私たちは、世界の地震の2割が発生する地震大国に生きている。耐震社会の構築に邁進していきましょう」とあいさつした。
会場には、国土交通大臣の太田昭宏氏が駆け付け、耐震インフラの整備の必要性について語った。前経済産業省副大臣の菅原一秀氏と、住宅金融支援機構副理事長の河村正人氏もあいさつに立った。続いて国土交通省 住宅局住宅生産課長の伊藤明子氏が「消費税増税とリフォーム支援策について」と題し、中古住宅流通・リフォーム市場拡大への支援策について講演した。
伊藤氏は、社会の少子高齢化に伴い、「若者はアパート住まいから始まり、将来は郊外の一戸建てに住むという『住宅双六』は終わった。高齢者が便利さを理由に都心に住み替えるなど、新たな住み替え需要が生まれる可能性がある」と指摘。「日本の住宅の平均築年数は諸外国に比べて短く、住宅ストックについても約5000万戸のうちの約1000万戸に耐震性がない。そのため経年劣化で築20年の住宅は市場価値がほぼゼロになってしまう。リフォームによって耐震性が上がれば、きちんと評価され取り引きされる方向を目指している」と話した。
そのためのリフォーム施策として、今年度補正予算と26年度当初予算で実施する「長期優良化リフォーム推進事業」について説明。「リフォーム工事前にインスペクションを行って維持保全計画を作成し、ある一定のリフォーム工事を行う住宅工事に対して、補助率3分の1で、一戸当たり100万円を補助限度額として国から補助する事業を実施します。最低限、劣化対策と耐震性は確保していただき、その上で省エネや維持管理などを伴う工事を行う住宅工事を募集。約5000万戸のストック住宅に対して、耐震性による安心・安全を確保し、それがきちんと流通する仕組みづくりを進めていきます」と述べた。
講演では、元自衛官で参議院議員の佐藤正久氏が、東日本大震災の被災地の現状報告と耐震の重要性について述べた。また、建築研究所環境研究グループの桑沢保夫上席研究員が、既存住宅の省エネ改修についての講演を行った。
必要なのは命を守る耐震インフラ

来賓あいさつ ◆ 太田昭宏 国土交通大臣
今から50年前の昭和39年、東京オリンピックが開催された年の6月に新潟で大地震が起こり、液状化現象という言葉が日本で初めて使われた。私はその年に京都大学土木工学科に入学し、耐震工学について学んだ。それ以来、耐震が大事だと言い続けている。
2002年からは、学校の耐震化が重要だと主張している。文部科学省の調査の結果、当時の学校の耐震化率は44パーセントだった。学校の耐震化は子供の人命に関わるし、学校は避難所にもなる。学校耐震化の推進に取り組み、現在では9割超まで学校の耐震化が進んでいる。
日本は地震国であり、災害も多い。平地は少なく、台風があり、土砂崩れがあり、災害が局地的に発生する。昨年の伊豆大島の地震では、今までになかった表層崩壊という現象が起きた。災害が局地的、集中的、激震的に起きているのに、なぜ直視しないのか。首都直下型地震、南海トラフ地震にどう対応するのか。各地の直下型・活断層型の地震にどう備えるのかを考えずして、この国の「命の安全保障」はできない。
防災減災ニューディール政策をとることが大切と主張している。昭和30年代の公共工事は産業整備だった。昭和50年前後は住居、下水道などの生活インフラ整備の時代だった。今、同じような感覚で公共事業を考えてはだめだ。首都直下型地震や南海トラフ地震にどう耐えるかを考えなくては、この国を守ることができない。
高度経済成長時代の構造物が劣化し、昭和56年の旧耐震基準の建物が今もあるのが現状だ。防災、減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化を公共事業のメーンストリームにしなければならない。
この記事の関連キーワード : リフォーム 中古 中古住宅 予算 住み替え 住宅金融支援機構 国土交通省 地震 増税 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 木耐協 木造 東京オリンピック 東京都新宿区 東日本大震災 省エネ 耐震 長期優良化 高齢者

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- WEB限定記事(2025/11/18更新)
- WEB限定記事(2025/11/18更新)
- WEB限定記事(2025/11/07更新)
- WEB限定記事(2025/11/07更新)
- WEB限定記事(2025/11/04更新)