東京都健康長寿医療センター(東京都老人総合研究所)
髙橋 龍太郎 副所長
浴室や脱衣室を暖め、ヒートショック予防
高齢者の冬場の入浴は、死に至るリスクを伴う―――。老年医学の権威である髙橋龍太郎・東京都健康長寿医療センター副所長は、こう警鐘を鳴らす。暖かい湯船につかるという、日本の入浴文化は健康増進に効果があるが、一方で高齢者の体には負担にもなるという。髙橋氏は、浴室をはじめ、住居内の温度を適切に管理することで、入浴による急死の原因である「ヒートショック」を予防できる、と提言している。
――― 聞き手/本紙社長・加覧光次郎
入浴によるCPAの救命率は1%以下
―――多くの高齢者にとって入浴は楽しみですが、特に冬の入浴には命の危険が伴うこともある、と先生は注意を促しておられます。
当センターが東日本の23都道県にある消防本部を対象に、入浴中に心肺停止状態(CPA)になって救急搬送された事例を調査したところ、2011年中には約4300人の高齢者が入浴中に亡くなっていることが分かりました。80歳以上が6割近くを占め、75歳から79歳がそれに続いています。このデータから、日本全体での入浴中の死亡者は1年間で1万7000人に上ると推計しています(図1)。
【図1】高齢者の入浴中の死亡者数(2011年)

―――交通事故による死亡者が5000人以下ですから、入浴中の急死の数がかなり多いことが分かります。
入浴中の死亡に関しては、大規模な実態調査はほとんど行われていませんでした。1999年10月から2000年3月にかけて、東京消防庁が機関決定し、私が委員長となって実態調査を行いました。全救急隊に調査協力を依頼して、救急要請の現場が浴室であった場合、救急患者の病状や年齢などを調査票に記入する「前向き調査」を実施しました。そのデータをもとに、全国の年齢構成の違いを考慮し、当時、全国で1万4000人が入浴中に急死していると推計しました。
それ以前は、県レベルでの調査はありましたが、東京のような、日本の全人口の約1割をカバーするデータはなかったのです。これは推定の数値ではありますが、一般に「溺死」と報告される数より、かなり多いことが分かりました。
―――厚生労働省の統計では、家庭内で起きた不慮の事故のうち、溺死で死亡したのは、年間約4000人というデータです。
厚生労働省の「溺死」のデータは、外因死、つまり死亡診断書に「浴槽内での溺死・溺水」と書かれたケースの数値です。しかし、入浴中の死亡者数は、溺死統計のみでは実態把握はできません。なぜなら、浴室で亡くなっていても、医師が心不全と判断すれば、内因死、つまり病気による死亡と分類されるからです。
東京消防庁が行った調査で、溺死という診断をされていない人も含めると、やはり4倍近い数字が出ます。交通事故による死者数が減っているのに、入浴中の急死はむしろ増えている、と言っていいと思います。
―――予防策を立てるには、正確な実態把握が必要ですが、実際には難しいと伺っています。
浴室はプライベートな空間なので、正確な死亡原因を調査するのは難しいのです。東京消防庁の調査では、病院と救急隊が協力して、事例を調べました。それで、入浴中のCPAの救命率は1%以下、ということが分かりました。浴槽内で心肺停止状態になると、湯船の水に溺れることなどが理由だろう、と考えられます。現場で死亡したことが明らかになると、多くは病院に搬送されません。いわゆる「社会死」と呼ばれます。これが入浴中にはかなりあると考えられます。しかし、亡くなった方のご家族にとって非常に微妙な話なので、その実態を調べるのはかなり困難だと言えます。
―――日本人はお風呂好きですから、冬の入浴が危険なのは問題です。死者数が増え続けているため、国も実態調査に乗り出しました。
日本救急医学会など3つの学会が、厚生労働大臣に実態解明の要望書を提出したことで、厚生労働省が2012年から調査を始めました。日本は諸外国に比べ溺死者数が多く、その多くが家庭内で発生し、しかもほぼ80%が高齢者です。これは、世界的に特異な状況です。今後は後期高齢者人口が急増し、入浴中の急死がさらに増えることも予想されますから、原因究明が進むことが望まれます。
湯温は41度以下、声掛け入浴も効果
―――浴槽の熱い湯との温度差で体に負担がかかり、「ヒートショック」のために命を落とす危険もあります。ヒートショックとは、どのような症状を起こすのですか。
ヒートショックとは、温度の急激な変化で血圧が上下に大きく変動することなどによって起こる健康被害ととらえることができます。失神したり、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を起こしたりします。特に冬場の入浴中に多く見られます。
―――冬の入浴中に多いのはなぜですか。
冬場の暖房が利いた部屋から出て、寒い脱衣室で衣服を脱ぐと、急激に体表面全体の温度が10度程度下がります。そうすると、私たちの体は寒冷刺激によって血圧が急激に上がります。この血圧の急上昇が、心筋梗塞や脳卒中を起こす原因の1つと言われています。
一度急上昇した血圧は、浴槽の暖かい湯につかることによる血管の拡張で、今度は反対に急激に低下します。この急激な血圧の低下が、失神を起こす原因の1つとなります。浴槽の中で失神し、溺れて亡くなるケースは、入浴中の急死の典型例と言えます(図2)。
【図2】入浴中急死のメカニズムと対策
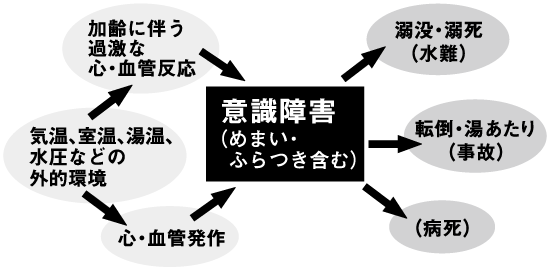
―――入浴中の死亡事故は、真冬の時期に多発しています。
外気温が低い12月と1月には、入浴中に心肺停止状態となる人が急増することが分かっています。最も多いのが1月の779件で、最も少ないのが8月の71件と約11倍の差です。冬に多い原因は、ヒートショックによるものと言えます。(図3)。
【図3】入浴中の心肺機能停止者数(2011年)東日本23都道県379消防本部
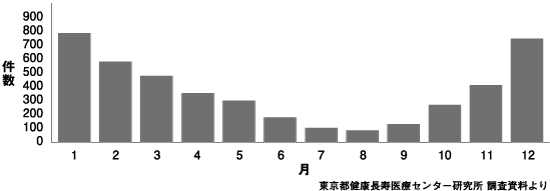
―――ヒートショックを防ぐ方法は。
冷えやすい脱衣室や浴室を暖かくすることで、ヒートショックは予防できます。専用の暖房器具などを使って安全に暖めてください。シャワーで浴槽へお湯をはって浴室全体を暖めるのも、今日からすぐできる対策です。トイレも体を露出させる場所なので、暖かく保つ工夫をすると安心です。浴室の断熱改修も効果的です。窓まわりは熱が逃げやすいので、内窓を設置すると暖かさを保つことができます。浴室をユニットバスに改修することでも断熱性は向上します。
―――お風呂の入り方を注意することでも予防できますか。
お湯の温度は41度以下にしておくことを勧めます。食後1時間以内や、お酒を飲んだ時は、血圧が下がりやすくなるため、入浴は控えた方がいいですね。
―――ヒートショックに注意した方がいい人は。
高齢者は特に注意すべきです。健康な方でも、高齢になると血圧が変化しやすく、体温を維持する生理機能が低下しているためです。注意してほしいのは、入浴中の急死例のほとんどが、介護のいらない、自立して生活している健康な高齢者で起きていることです。要介護状態にある人の多くは、一人でお風呂に入ることはできません。誰かが見ていれば、浴室内で亡くなることはありません。ですから、高齢の方は家族による声掛けを、一人暮らしの方は日帰り温泉などを利用した方が安心です。
―――先生もテレビに出演して注意を促しておられるので、ヒートショックという言葉は、かなり知られてきました。
ヒートショックという言葉は、実は医学用語ではありません。医療関係者が使い始めた言葉ではなく、建築や住宅関連の方面から出た言葉ではないか、とも考えられます。私も最初は、曖昧な言葉なので、取材を受けても使いませんでした。ただ最近は全報道機関が使うようになりました。「急激な温度変化によって、特に入浴中を典型とした死亡などの健康被害」というような意味で、大きな誤解はないので、私も使っています。
―――2013年12月、歌舞伎俳優、中村獅童さんのお母様が、自宅の浴室で亡くなりました。
有名人のケースが報道され、自分の近所に入浴中に亡くなった方も結構いるので、関心を持ってくれていると思います。私の見ている限りでは、ほぼ8割の高齢者が、ヒートショックという言葉を知っていて、「冬のお風呂は危険だよね」と話しておられます。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面




















