【ハウズ・ジャパン×Tunnel 対談】 「家に帰るのが楽しみ」、ITで実現を

ITは住宅業界をどのように変えるか―。アメリカ発の住宅情報サイト「Houzz(ハウズ)」を運営するハウズ・ジャパンの加藤愛子社長(33歳)と、部屋写真のSNS「RoomClip(ルームクリップ)」のTunnel高重正彦社長(33歳)が対談。「住宅×IT」分野で活躍する2人は、何を変えていくのか。
Houzz Japan
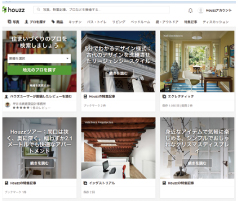 アメリカで2009年に誕生。日本では2015年から開始。設計士、工務店、インテリアコーディネーターなど住まいのプロと、一般ユーザーをつなぐプラットフォーム。全世界で4000万人が利用する。
アメリカで2009年に誕生。日本では2015年から開始。設計士、工務店、インテリアコーディネーターなど住まいのプロと、一般ユーザーをつなぐプラットフォーム。全世界で4000万人が利用する。
RoomClip
 2012年に開始。部屋の写真を投稿し、その作り方を共有する「住宅版クックパッド」。女性を中心に、月間200万人が利用、累計投稿写真数は180万枚にも上る。
2012年に開始。部屋の写真を投稿し、その作り方を共有する「住宅版クックパッド」。女性を中心に、月間200万人が利用、累計投稿写真数は180万枚にも上る。
生活の記録が暮らしを豊かに
高重 なんでルームクリップをやるようになったのかとよく聞かれるんですが、2011年3月の東日本大震災があったじゃないですか。実家が福島県いわき市で、要は被災の地域だったんですね。両親とか家は大丈夫でしたが、その後引っ越しで実家を引き払いました。僕自身、すごく実家に愛着があったわけじゃないんですけど、いざなくなってみるとそこに蓄積されてきた自分の色んな工夫とか思いみたいなのが一瞬でなくなって、それってもう二度と自分では参照出来ないんだなっていう風に感じまして。その時に、家って人間にとって人生を表す場所だし、人生に影響を与える場所なのに、あんまり自分の家っていうものを振り返る機会もなければ、他人の家を見る機会がないよねって、すごく感じました。でも意外とインターネット上にパーソナルな生活を記録して共有して人に見せる場所がなくて、それがあったら人間の生活ってとても豊かになっていくなとイメージが湧いて。それでルームクリップという事業をやることになりました。
加藤 すごい素敵な話ですね。私は日本生まれなんですけど、アメリカ育ちで海外が長かったんですよ。現地で大学を卒業してからは、金融会社に入りました。当時日本株の営業をやっていたんですけれども、日本の事業について語るんですよね。こんな素晴らしい会社があるとか、こんなすごいプロダクトがあるとか。そういう風に語っているものの、結局自分では全くその事業になんのインパクトも与えていないんですよ。それに物足りなくなって。化粧品関係の企業で働いたり、日本発のベンチャー企業のお手伝いをしていたんですけど、全ての共通点というのが、日本と海外をつなげる、その架け橋になるっていう仕事でした。ハウズもそうです。当時2500万というユーザーがいて、そのプラットフォームを活用して日本の素晴らしい技術や職人技を、必要としているマーケットと繋げてあげることができるのではないか思い、ハウズに携わることになりました。
家づくりってもっと楽しい
高重 今回の対談のテーマが「ITで何を変えたいか」ということなのでお話しさせていただくと、会社のミッションとして、「日常の創造性を応援する」っていうのがあります。
日常の中で特に家ってその一番の中心地だと思うんですよね。僕らが生きていることのほとんどが家の中で行われているだけど、特に日本だとあんまり創造的な場所にはなっていない。退屈な場所だったり、ある種の出口がない場所というイメージがあって、そこで創造的な瞬間がどんどん訪れるようになっていけば、人間って本当にすごく豊かになると思っています。
あと僕も含めて結構人間って弱いと思っていて、日々生きていく中で、俺、駄目だな、みたいに思うことって多い。その時に、対抗手段になりうるのって創造性を発揮することなのかな、と。創造的な事が出来れば、自分は全然価値のない人間ではなくて、自分の人生って特別かもしれないと。こういう自分の人生が変わるんだっていう体験を、小さくてもいいから常に供給し続けるというのが、僕らが役割だというふうに思っています。
加藤 すごく共通点がたくさんあるなと思うのが、当社も世界中で目指しているのが、「もっと住まいづくりは楽しいものであって実は怖いものじゃないんだよ」というのを根付けたいんです。
共通していると思うのは、家のことで悩んでいる人や疑問を持っている人を勇気づけられるということ。当社のプラットフォームに来てくれて、掲示板に質問すると他の人がどんどん答えてくれるんです。どこにも答えが見つからなかったものが、ようやく見つかったっていうようなところはすごく似ているなと感じます。私の個人的にやりたいことで言えば、寝に帰るだけの家をとにかく減らしたい。本来であれば、自分がうまく表現されているような住環境がある
はず。そして自分のライフスタイルや家族構成、住まい方の変化に合わせて、どんどん家も進化していくということ
を、もっと文化として根付けていきたいなと思っています。
高重 僕もすごく共感します。本当に寝に帰るだけの家を、というのはまさにそうだなと思っていて、本当に家に帰るのが、もっと楽しみになればそれだけで人生絶対に良くなるはずなんで。
加藤 そうですよね、楽しみになればやっぱりお友達とか、職場の人を家にも来てよって誘いたくなりますよね。
ユーザーが付加価値生む
高重 ユーザーってありとあらゆる想像を超えてくるっていうのがパワーだと思っています。超身近な例で言えば、クライアントさんの収納をウチのユーザーさんが使ったことがありました。服を入れるために作られた普通のプラスチックの収納だったんですけど、これをユーザーさんは子供のおもちゃ箱として使ったんですね。
子供が簡単に出せて入れやすかったから、子供のおもちゃ箱としてすごく便利ですっていう意見が盛り上がったり、そこにちょっとシール張って自分ぽくしたりみたいな人が出てきたりして。色々ユーザーのインサイトを集めても、僕はやっぱり商品を作ることはプロの仕事だと思っています。でもその商品が世の中に出た後に、色んな付加価値を付けるのは、むしろユーザーが得意だと思っています。
だから自分たちのことをディスラプター(既存産業を破壊する企業)だと思っていなくて、むしろ既存の枠組みの中でどれだけ市場を大きくできるのかっていうふうに位置づけています。
加藤 おっしゃる通りで、ユーザーもプロも同じような形で、新しいものをどんどん作っていくということが可能だと思うんですよね。ただこれまでは、アマチュアは情報や知識がそれほどなかった。そこの知識レベルを上げてあげて、個々のクリエイティビティをつなげることによって全く新しい住まいづくりっていうことが今後できていくんじゃないかなと思います。ハウズにはもちろん画像がたくさんあるんですけれども、何よりもコミュニケーションをより簡単にできるためのツール。プロの方が設計した家のお写真から、素人の方が選び、うまく自分が欲しいものを伝えられるためのコミュニケーションをしっかりと取れる。
これまでかなりギャップがあった知識レベルを、もうちょっと狭めてあげるようなツールでもあるので、たぶんそこがハウズが目指している所だと思うんですよね。

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- 1679号(2026/01/05発行)15面
- 1679号(2026/01/05発行)35面
- 1679号(2026/01/05発行)31面
- 1679号(2026/01/05発行)33面
- 1679号(2026/01/05発行)8,9面



















