東日本大震災から着実に復興への道筋を歩んでいる町々がある一方で、依然手をつけかねたままになっているところもある。あまりにも広域にわたる甚大な津波被害のため、今まで地震それ自体の被害には注意が払われてこなかった。阪神・淡路大震災に比べると幸い地震の被害は少なかったと言われる。本当にそうなのだろうか? 最近の地震研究を中心に地震被害について検証し、今後のリフォーム提案に役立てていきたい。
仙台市の耐震は頭抜けて進んでいた
「古い住宅で倒壊した事例が見られる」「瓦が落ちた」「ヘアクラックが見られた」「壁が剥落した」のような被害事例が報告される一方で、"地震の揺れによる住宅の被害"についてまとまった検証は行われていない。これはとりもなおさず、地震による被害が少なかったからとする向きもある。これには主に2つの理由があると言われている。
1つは、東北地方の耐震化率の高さが挙げられる。1978年の宮城県沖地震を経験した東北地方では、自治体が強力に耐震化を促進しており、一例を挙げれば2008年の時点で仙台市の住宅耐震化率は83%となっており、全国平均の78.8%よりもかなり高くなっている。公的機関・施設での耐震化も盛んで、学校はほぼ90%を超えていた。これらの耐震化は主に1980年の新耐震基準に準じていると考えられており、改めて新耐震の効果が確認されたと言うこともできるかもしれない。
キラーパルスが木造を襲う
もう1つの理由が地震動の周期の違いだ。東日本大震災直後、また昨年末にも一部のマスコミが取り上げた「キラーパルス」という地震動がある。キラーパルスとは周期が1~2秒程度の短い周期の地震動を指す。これを「稍短周期地震動」と呼ぶ。
地震動の周期が「長い」「短い」とは、振幅の幅の違いだ。例えば地震が起こり始めるときの「カタカタカタ」とした小さな震動。これは振幅の幅が1秒以下で非常に短い状態だ。こうした震動の周期が、物質が持つ固有振動数と同じ帯域になるとその物質も大きく揺れるということになる。つまり共振だ。
木造住宅の固有振動数は1秒から2秒前後とされており、同じ周期を持つキラーパルスが発生すると木造住宅に大きな被害をもたらす。図を見てみよう。東大地震研究所が東日本大震災直後に発表した振幅数の比較である。これによると、阪神・淡路大震災のときは、このキラーパルスの震動が非常に多かったために木造住宅の被害が甚大になり、東日本大震災では少なかったために被害が比較的、少なかったということになる。
≪図1≫地震変動周期の比較

▲阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)と東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の周期を比較したもの。前者が1秒前後の周期に高い数値を検出しているのに対し、後者は1秒以下の短い周期でゆれが観測されている。
地震周期が違えば大きく被害が変わる
このことで明らかになるのは、一定水準の耐震化があった上での議論になるとはいえ、震度が大きければ住宅被害が大きくなるとは限らない、ということだ。
これは2012年に入ってから表面化してきた、中高層住宅の地震被害の問題からも見えてくる。当初、東日本大震災の中高層マンションなどの被害はほとんどないという報告があったが、後々罹災証明ベースで検討していくと、倒壊に匹敵する被害の発生が少なくともあることが確認されている。
東日本大震災の揺れは、キラーパルスこそ少なかったが、その前後の短周期、長周期の震動が大きかったという説がある。短周期は剛性が高いもの=硬いものに対して強い地震力を発揮し、長周期は、水平震度は弱くなる傾向はあるものの、重い物質に対して地震力を発揮する。中高層住宅はその材質・構法の特性上「硬く」「重い」。このため、中高層住宅に被害が確認されたのではないかと言われている。
また、長周期の震動については、東京・新宿副都心の高層ビル群がゆらゆらと揺れた映像が大きな衝撃を与えた。東京・大阪などで検証が進められており、直後に起きる剥落などの被害は認められないが、建物中層部にねじれが起き、圧力がかかった可能性などが指摘されている(図2)。
≪図2≫工学院大学新宿キャンパスにおける地震観測
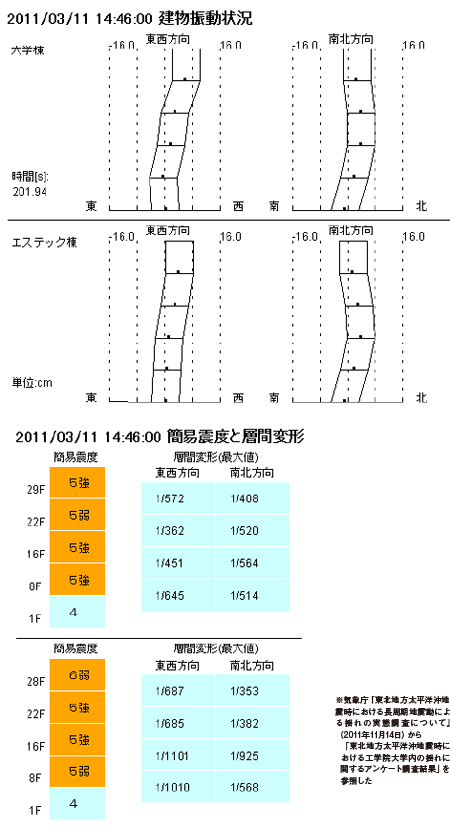
▲東日本大震災発生直後から、高層建築での地震動の研究が盛んに行われている。これは気象庁と工学院大学が行った調査結果を参考として掲載した。このビルでは中層階でもひずみが確認されていない。
「震度の周期」に対応した耐震化が肝要
このように、今までは震度だけで考えられてきた住宅被害が、震動の周期とも密接に関係していることが分かってきた。つまり、「震度が大きくても家が倒壊しない可能性がある」と言えるが、逆に「震度が小さくても周期さえ合えば、家は倒壊する」ということだ。ただ残念ながら、キラーパルスのような特定の周期の震動が起きるメカニズムはまだ分かっておらず、海溝型だから直下型だから起きる、とも起きないとも言い切れないのだ。
これからは、震度に対しての耐震を考えるだけではなく、建築物の材質・構造別に被害を与える、「振動の周期」に対応した耐震化も考える必要がある。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















