春が近づき、気温が高くなると様々な生物が動き出す。家の大敵シロアリも例外ではなく、4月から5月に飛来を始める。シロアリの被害を食い止めるためには、定期的な防蟻対策が必要です。そこで今回は防蟻施工の提案ポイントを紹介する。
被害に遭いやすいのは湿気の多い水まわり
まず、防蟻提案を行ううえでシロアリの生態を理解することが重要だ。日本には現在約20種のシロアリが生息しているが、国内に広く分布し家屋に被害を及ぼす代表的なのはヤマトシロアリとイエシロアリの2種類(図1)。そのほか、最近では『乾材シロアリ』の仲間であるアメリカカンザイシロアリとダイコクシロアリの被害が増えてきている。
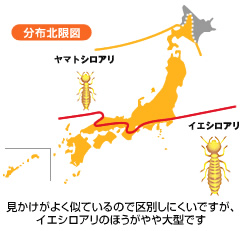
【図1】 分布北限図
見かけがよく似ているので区別しにくいが、イエシロアリの方がやや大型
シロアリが生きていくためには、人間と同じで水、食べ物、心地よい環境の3要素が不可欠(図2)。この3要素が揃っている環境こそ、最も「シロアリ被害に遭いやすい場所」となる。そのためシロアリ被害は、水を使用するお風呂場・洗面所・トイレ・台所の流し、その付近の土台・床・柱などに被害が集中しやすい。そのほか、地面から最も近いエサ場として、玄関まわりが被害に遭いやすい。
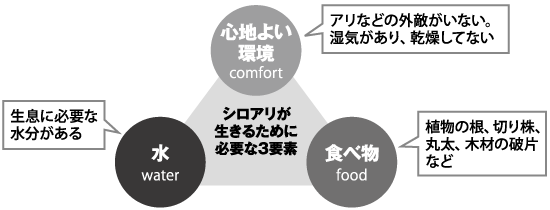
【図2】 シロアリが生きるための3要素
3つの要素のうち、1つでも取り除けばシロアリはいなくなる
また、最近増えている乾材シロアリは、大量の湿気がなくても木の中だけで生きられるので、天井裏から床下までのすべての木材、家具、木製品が被害を受ける可能性がある。
環境や家族にやさしいベイト工法
では、シロアリ防除はどのように行えばよいか。方法にはいろいろあるが、代表的な方法は2つだ。
まず1つ目は、昔から行われてきた薬剤を散布するバリヤー工法(図3)だ。基礎や土台、柱などに直接薬剤を散布する。コストが安く、選べる薬剤も豊富。効果の期間が5年以内と定められているので、少なくとも5年おきの定期施工が必要となる。
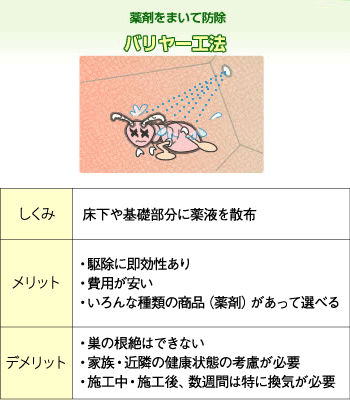 【図3】バリヤー工法
【図3】バリヤー工法
2つ目は、薬をまかず普段の生活のままできるベイト工法だ。建物の敷地内に薬剤入りの餌を埋め込む方法(図4)。
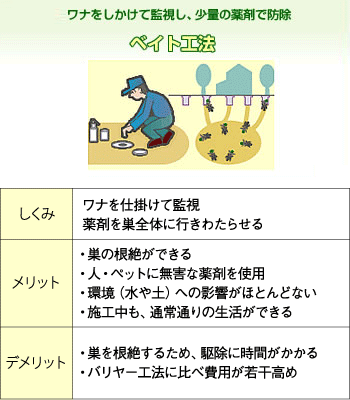 【図4】ベイト工法
【図4】ベイト工法
シロアリは新たな餌場を見つけるとフェロモンにより、その餌場に仲間を誘導する習性がある。ベイト工法はこの生態を利用した工法で、シロアリが好むように調整した薬剤を使用し、つぎつぎと薬剤を摂取させる。薬剤入りの餌を コロニー(巣)のシロアリ全体に薬剤が行きわたることにより、シロアリを巣ごと壊滅させるしくみだ。
薬剤を散布しないため安全性が極めて高く、犬や猫などペットがいても安心して提案することができる。作業員が年に少なくても4回は点検に訪問するので、施主との関係が深くなるし、営業システムとしても注目されている。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















