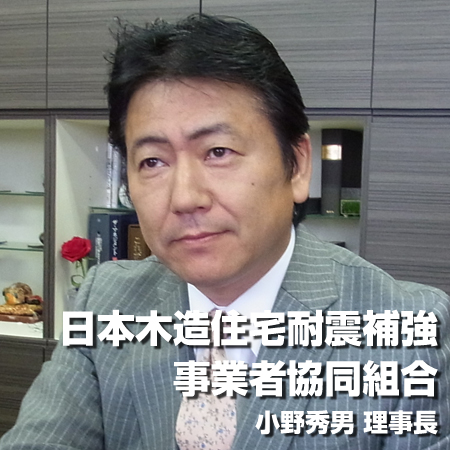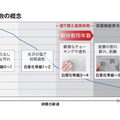日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 小野秀男 理事長
東日本大震災から1年余り。人々は津波の衝撃からようやく落ち着きを取り戻し、"揺れの怖さ"という地震本来の脅威に目を向け始めている。耐震社会の実現を目指して活動する日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(以下、木耐協)では、今年に入ってから耐震診断、改修の件数が急増しているという。小野秀男理事長に、近況と今後の見通しを聞いた。 東日本大震災から1年余り。人々は津波の衝撃からようやく落ち着きを取り戻し、"揺れの怖さ"という地震本来の脅威に目を向け始めている。耐震社会の実現を目指して活動する木耐協では、今年に入ってから耐震診断、改修の件数が急増しているという。小野秀男理事長に、近況と今後の見通しを聞いた。
静かに広まる「耐震」意識
―――今年に入って耐震診断、改修の依頼件数が急増していると聞きましたが、実際に市場でどんな変化が起きているのでしょうか。
まず第一に、耐震診断後に改修を行う補強率が予想以上の増え方をしたのが大きな動きです。2010年の1月から東日本大震災が起きた2011年の3月11日前までのデータでは、補強率は約27%でしたが2011年3月11日以降は39・5%に上昇、約1・5倍です。
―――診断件数自体も増えていますか?
実は大震災発生後も、2011年は前年と比べても微増程度でした。それが、今年に入ってから大きく伸びました。ここ5〜6年は年間で5~6000件の診断だったのですが、今年は3月だけで1000件、すでに1月から4月までの合計で3000件を超えています。
―――なぜ1年近く経ってからなんでしょうね?
それは東日本大震災の被害が圧倒的に「津波」によるものだったからだと考えられます。地震としては発生確率が99%と想定されていたものが来た、というに過ぎないのです。しかし今回は、実際地震で倒壊した建物もさほど多くはないのに、津波の被害が余りにも大きすぎた。人はあまりにショックが強いとすぐには動けないですから、半年以上たって、ようやく自分たちのことを考えられるようになったということじゃないでしょうか。
―――確かに昨年はあまりのショックで自分の家のことまで気が回らなかったかもしれませんね。
加えてもうひとつの要因が報道です。震災以降、各地方自治体が被害想定の見直しをして、昨年末くらいから「直下型地震がきたら」「震度7以上の揺れが起きるのは」という報道が多くなったことも大きい。津波から地震本体に意識が向いたというところでしょう。
―――そういう意味では今年のマーケットの動向は、ちょっとこれまでなかった動きかもしれませんね。
木耐協は阪神大震災の木造建築事業者としての反省を受けて発足して、今年で14年目になりますが、年間の耐震診断件数は、1998~2004年までは年間1万2000件。そのピークは、新潟中越地震直後の2005年で2万4000件でした。その後、実は何度か震度5強以上の大きな地震があったにも関わらず、診断申し込みが大きく伸びることはありませんでした。地震に対する"慣れ"が生じているのかもしれません。ですが今回は、新潟中越地震直後のようにすぐ反応があったわけではないですが、じわじわと反応が大きくなっています。
新耐震建物の83%が1.0未満
―――もうひとつ、耐震基準の問題もニュースになりました。新耐震基準でも倒壊する、という報道です。
もともと耐震基準は、1981年の大改正を境に「旧耐震」「新耐震」と便宜的に呼ばれていますが、当組合では設立以来、建築年度として2000年までの木造住宅について耐震診断を行ってきました。旧耐震は古い耐震基準で、1981年より前に作られた建物が該当します。耐震基準の評点で1・0以上あれば倒壊しないと言われていますが、現行基準に照らし合わせて診断すると、旧耐震の建物の97%が1.0未満なのです。では、新耐震、つまり1981年以降2000年までの建物なら大丈夫なのかというと、実は83%の建物が1・0未満、倒壊の可能性があるという結果が出ています。新耐震の建物であっても対策が必要な場合も多いのです。
―――つまり、新耐震神話の崩壊ですね。ちなみに耐震基準はこれまでどのように改正強化されてきたのでしょうか。
崩壊と言えるかどうかは別として、新耐震でもそれぞれの建物に優劣が有る事は事実です。1981年からの新耐震では圧倒的に壁の量が増えました。壁量規定が大幅に見直されたんです。これで倒壊しないだろうと思われたところに、1995年、阪神大震災が起きました。公的な発表では旧耐震の建物がずいぶん倒れたとされていますが、実は新耐震の建物も相当数倒壊しているのです。調査によると、ホールダウン(ホゾ抜けを防ぐ接合具)が使用され構造計算が行われた3階建て木造住宅は搭状型であるにも関わらずほとんど倒壊しなかったことが分かり、それから5年後に新耐震がさらに強化されました。これが2000年に出た俗にいう「新・新耐震」です。
―――新・新耐震では何が変わりましたか?
ひとつは先ほど挙げたホールダウンの標準仕様化ですが、もうひとつ、壁のバランスに主眼が置かれました。つまり、壁の量が増えても、その配置バランスが悪いと倒壊の可能性が高くなってしまう。日本の家屋は水回りのある北側は壁量が多いのですが、南側は採光を良くしようとするあまり壁の量が極端に少ないケースが見られます。これだと、南側が大きく揺れてしまいます。そのため、壁の配置バランスを考えるようになりました。
―――新・新耐震の住宅ならまず安心と考えてよいわけですね。
そうですね。
耐震診断・改修のこれから
―――現在、既築住宅のうち旧耐震:新耐震:新・新耐震の建物の比率は3:4:3と言われています。今まで進められてきた耐震診断・改修の主な対象は旧耐震の3割だったと思いますが、今後は新耐震も対象にする必要があるということですね。
木耐協では設立以来14年間、組合員の1000社のみなさんと、旧耐震に限らず新耐震についても耐震診断を行ってきましたが、その実績は累計15万件になろうとしています。地震被害から1人でも多くの命を守る為に、さらに多くの人に耐震に意識を向けてほしいと思います。
実は、今年に入ってから、チラシの反響が大変良くなっています。通常チラシの反響は5000分の1、3500分の1もあれば上出来ですが、今年は平均2000分の1くらいで反響があります。東京大田区の組合員では、3万3000枚チラシを配布したところ54件もの診断申し込みがありました。実に611分の1の反響率。うれしい悲鳴です。
―――耐震診断数だけでなく、実際にそれを工事に結びつける補強率を上げる取り組みが大事ですよね。全国の自治体が補助金を使って地元の建築士などに委託して行っている耐震診断の場合は、それこそ実際に補修工事にまで結びつくのはわずか3〜4%しかないと聞いています。その点、木耐協の場合は3〜4割ですから、率は極めて高い。
木耐協の組合員のほとんどは施工業者です。阪神大震災をはじめとする地震災害を経験し、木造住宅に携わる私たちがすべきことは何なのかを考えた時、家を造る仕事が医者と同じく命を預かる仕事だと考えたら、いつ起きてもおかしくない地震に対する備え、耐震補強を行ってほしいという想いが強くなるのです。だから補強の説得にも力が入ります。
―――その想いの強さが工事受注に結びついているんでしょうね。
しかし、気持ちだけでは人は説得できませんから、木耐協では施工技術や営業技術を磨くための様々な研修会も行ってきました。組合員によっては11年間で2000件も耐震診断・耐震補強をしているところもありますので、そのような組合員とノウハウを共有して、補強率を上げる努力もしています。
―――耐震補強の費用が高いことも、補強率が上がらない理由になっているのではないでしょうか。
そうですね。木耐協が行う耐震補強の平均単価は約150万円ですが、自治体が出す補助金は大体どこも30万円程度。そうなると120万円は自己負担です。起きるかどうか分からない地震に対する工事に、それだけ出すのは躊躇する人も多いですね。それに補助金の30万円をもらう為の条件が厳しいのも問題です。これも自治体によって異なりますが、評点を1・0以上にする工事でなければ補助が出ないところが多い。しかし、旧耐震の建物の評点を1・0以上にするには、実際には300万円以上かかることもあります。それで30万だけ補助してもらっても...となるわけです。
―――本来、一番大事なのは建物より人の命ですから、せめて「圧死」を防ぐための手立てはできないものでしょうか。
ええ、どうしても完全に補強するのが難しいのであれば、仮に被害を受けたとしても、そこに住んでいる人が生き延びる率を上げるような工事を行う「減災」の発想で取り組むことも必要でしょうし、そうした減災に対応した枠組みを政府や行政で考えていくことも必要になるかと思います。

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- 1673号(2025/11/17発行)12面
- 1671号(2025/11/03発行)3面
- 1670号(2025/10/27発行)24面
- 1669号(2025/10/20発行)21面
- 1667号(2025/10/06発行)6面