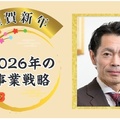建築研究所と日本サステナブル建築協会は第15回住宅・建築物の省CO2シンポジウムを2月12日、東京・水道橋すまい・るホールで開催した。
はじめに、事業の評価委員会委員長で建築環境・省エネルギー機構理事長の村上周三氏が次のように挨拶した。「約5700万戸ある住宅ストックの断熱性能を見ると、いまだ76%が旧基準、無断熱の住宅。建築技術の改善や普及にはクライアント、設計者、施工者などの意識のバリアがあり、なかなか進んでいない。平成20年度に始まったこの事業で既に200件あまりのプロジェクトが採択されており、それは日本の建築界の大きな財産。こうした先導的な技術や取り組みが日本全国、さらに海外まで波及していくことを願っている」
次に国土交通省住宅局住宅生産課の村上晴信企画専門官から、住宅ストックの省エネや省CO2面の質の向上、流通促進等への国の施策についての説明が行われた。
また評価委員3人からプロジェクトに対する概評が述べられたが、東京大学大学院准教授の清家剛氏は「新築住宅に省エネ基準を義務化しても、既存住宅の改修が進んでいかなければ全体のエネルギー使用量は変わっていかない。先導事業による新しい切り口が今後の普及、促進につながれば」と訴えた。
その後、昨年12月に結果が公表されたプロジェクトの事例や、過去に採択され完了した例が発表された。
なお平成26年度第2回の先導事業には17件の応募があり、地域工務店グループ・e-ハウジング函館が提案した「北海道道南の地域工務店による北方型省CO2住宅の新展開」等の10件が採択された。各プロジェクトには、対象費用の1/2(戸建住宅の場合は1戸あたり300万円が上限)の補助が出る。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
WEB限定記事(2026/01/05更新)
-
1679号(2026/01/05発行)17面
-
WEB限定記事(2025/12/29更新)
-
WEB限定記事(2025/12/17更新)
-
1677号(2025/12/15発行)01面