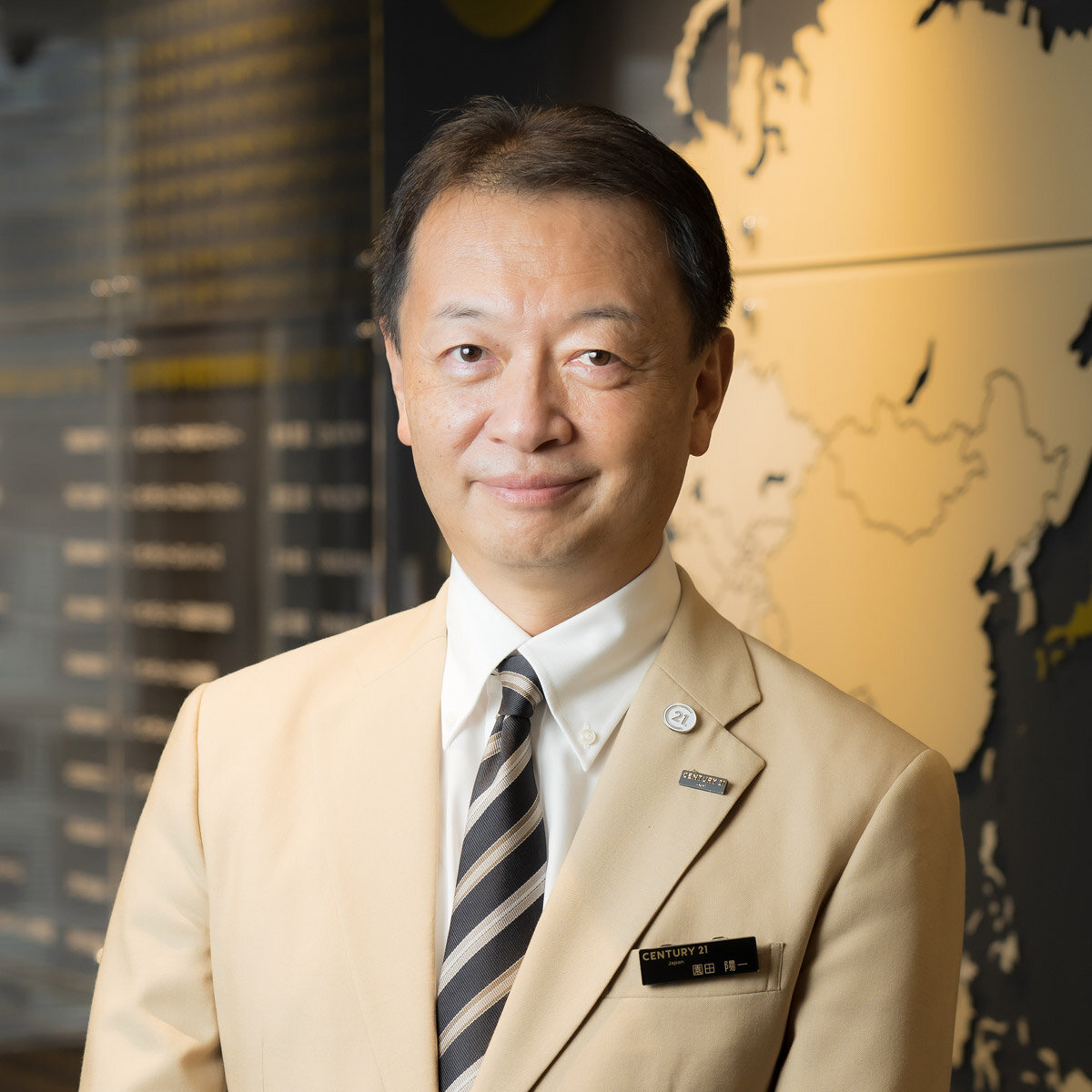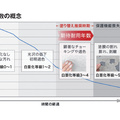センチュリー21・ジャパン 園田陽一 社長
日本国内に加盟991店(2022年3月末現在)の不動産ネットワークを展開するセンチュリー21・ジャパン(東京都港区)。2022年3月期の売上高は前年度比3.6%減の37億2600万円、営業利益は8.1%減の8億6700万円と減収減益だったものの、コロナ禍にありながらフランチャイズ(FC)業態の強みを生かし、加盟店数は過去最大の数字となった。不動産市場の今後や、2019年から本格参入したリフォームビジネスへの展望などを園田陽一社長に聞いた。
経営者同士が教え合う強み
――現在991店舗、コロナ禍でも昨年から11店舗増加しています。どんな理由で加盟店が増えたのでしょうか。
不動産仲介業を営む皆さんの考え方はさまざまですが、多少コストがかかったとしても加盟することで世に知られている看板が使えて、集客や教育研修など、自社だけでは手に入れられないものがしっかりと得られます。
コロナ禍もあり集客の手段も限定されていますし、物件が不足していると、より物元に近いところで仕事がしたいという方は多い。そのための営業をするにも、ブランドがあった方がアプローチしやすいですよね。私どもが40年で積み上げたシステムもブラッシュアップしていますので、今まで以上にFC加盟する会社は増えると自負しています。
――ブランド力が不動産営業のより重要なファクターになるということですね。加盟店同士の交流も加盟のメリットになっていると聞きました。
加盟店同士の交流がとてもさかんなのが特徴です。これは昔からですね。同じ制服を着て集まるというのも、仲間意識を持ちやすい理由の1つかもしれないです。新人経営者にとっては、さまざまな問題が起きると、そこにどう対処すればよいかとても迷います。弊社の加盟店経営者たちは不動産のプロで、社長業のかたわら自身も営業するトップセールスマンが多いので、彼らが積極的に解決法を教えてくれるのは強みです。
取引の分かりやすさが至上命題
――確かに、同じ制服は一体感を生みやすいと感じます。ところで、コロナ禍における住まい、働き方環境の変化で不動産市況がどうなってくと考えていますか。
人口と世帯数減のなか、職場と住宅との関係は大きく変わってきます。どこに住んでいても仕事ができれば職場に縛られない住宅という発想になり、住み替え回数の増加にも関わってくる。仮に人口や世帯数が2割減ったとしても、十分まかなえるだけのマーケットがあります。
――人口減少マーケットの中でも不動産取引需要は拡大するという予測ですね。そうした、取引拡大を推進するには、何が必要だと考えていますか?
いかに取引を分かりやすくしていくか。業界全体の話ですが、お客様にとってわかりやすい取引とは何かを追求すべきです。重要事項説明書にしても書類が多くて煩雑とか、住宅ローンの手続きも何を出せば良いかとか。これをデジタルの流れの中で変えていく必要があります。
リフォームビジネスの仕組み化へ
――今後変化する不動産市況に対する今後の取り組み、特に中古住宅売買とリフォームについてどんな展望をお持ちでしょうか。
古い家をリフォームで住みやすくしたいとか、世の中全体に古いものを大事に使おうという流れがあります。若い世代を中心に「自分の好きなように住めるなら、むしろリフォームや中古が良い」という声をたくさん聞きます。基本的性能が担保される仕組みさえあればニーズは膨らむので、この市場は伸びると考えています。
不動産業界は、リフォームというビジネスの入り口にいます。あとは、いかに仕組み化できるか。お客様の細かなニーズを拾い上げてデザインして形にする工程を、誰とどう分業するのか、あるいはすべて自分でやるのかという判断も加盟店には求められますが、両パターンを用意すべきだと思っています。
――今期1000店舗という1つのハードルを越えると思いますが、中長期の目標と戦略を教えてください。
まだまだ店舗数は伸びる余地があります。空中店舗も多いですし、契約は店舗に行ってというのはあるにせよ、もはや店舗の所在が必ずしも重要な意味をなさなくなっているので、そこは柔軟に対応していくつもりです。
不動産流通の発展の一翼を担いたいと思っているので、そのためにも、先ほどお話しした取引を分かりやすくすることは必須ですし、中古物件に夢を描けるためにも、リフォーム業界とのつながりを重視していきます。
(聞き手/報道部長 福田善紀)

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- 1675号(2025/12/01発行)12面
- 1673号(2025/11/17発行)12面
- 1671号(2025/11/03発行)3面
- 1670号(2025/10/27発行)24面
- 1669号(2025/10/20発行)21面