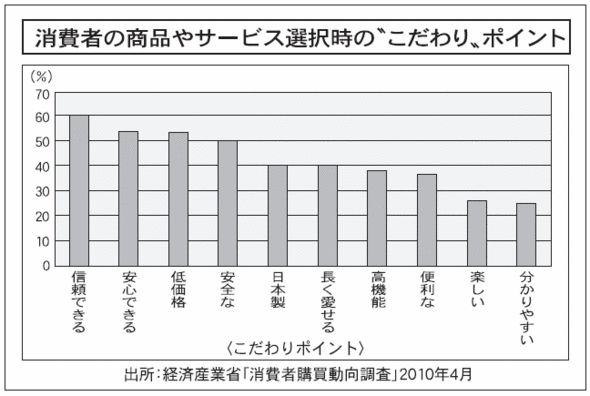明治大学 理工学部情報科学科 向殿(むかいどの)政男教授
1970年明治大学大学院工学研究科電気工学専攻博士課程修了。工学博士。1978年同大工学部電子通信工学科教授、1986年同大計算センター所長、1988年同大情報科学センター所長、1989年同大理工学部情報科学科教授。専門は安全学、情報科学。国土交通省昇降機等事故調査部会長。
◆スペシャルインタビュー◆
東日本大震災や高齢社会の進展を機に、日本は大量消費型の価値観から、良い物を長く大切に使うという価値観に変わりつつある。明治大学理工学部情報科学科の向殿政男教授は、安全を客観的、科学的に判断するための学問である「安全学」の権威。生活の中にあふれる製品を長く安全に使うには、消費者、企業、行政が安全に対する意識を高め、それぞれの役割を担うという「安全文化」を日本に定着させる時期に来ている、と向殿教授は提言している。 ≪ 聞き手:本紙社長 加覧光次郎 ≫
安全は科学、安心は価値観の問題
――震災を機に、消費者の価値観が変化し、「安心」と「信頼」が製品に求められる時代になりました。先生は、安全と安心を明確に分け、安全は科学的、安心は価値観の問題である、としています。安全学の視点から、ものを長く安心して使うためのポイントをお聞かせください。
私は講演会などで「絶対安全は存在しない」、安全には消費者にも責任がある、ということを話しています。何のリスクもない製品なんて、実はないのです。メーカーはリスクの少ない安全な製品を作る努力を重ねていますが、それでも必ずリスクが残っていますので、消費者自身がそのことを意識して使う必要があります。危険を伴う誤使用はマニュアルに書いてありますが、マニュアルを読まなかったり、なくしてしまったりすることもある。リスクの高い製品についてはラベルを貼るといった工夫をメーカー側も始めていますが、実は消費者にも責任がある、ということを啓発していかなければいけません。
――先生は経済産業省でリコールの問題に関わっておられます。2月にも、長崎市のグループホーム火災事故で高齢者が一酸化炭素中毒で死亡するという事故が起きました。火元とみられる加湿器が、TDK製のリコール製品だったといわれています。
あの事故は、リコール製品を使い続けていると重大事故につながることを再認識する事故でした。私は、現在のリコール制度にはいくつかの問題点があると考えています。1つは、リコール情報が消費者に十分に届かないことが多いということです。消費者は自分の家にリコール製品があるということを知らないし、リコール製品の危険性もよく分かっていません。これではリコール情報が出ても、製品を100%回収することはできないと思っています。
――リコール情報は消費者庁のサイトや新聞に掲載されますが、消費者に情報が十分に伝わる仕組みになっていない、ということですね。
もう1つは、トレーサビリティーの問題です。回収はメーカーの義務ですが、リコールになった製品を、誰がいつ買って使用しているかという情報がなければ、回収は不可能です。昔は街の電気屋さんがそういう情報を持っていて、リコールが出るとすぐ、買った本人が知らなくても電気屋さんが回収に行きました。今は家電量販店で買う時代ですから、メーカーが家電の使用者を特定するのはとても難しい。家電量販店はポイントカードでどんな商品を誰が、いつ買ったかの情報を持っていると聞いています。家電量販店とメーカーが手を結び、回収努力をする必要があると考えています。
安全に対する責任を消費者も自覚すべき
――ものを長く安全に使うための、消費者の役割は?
安全に対する責任は消費者にもある、という意識を持つことです。すべての製品には利便性と危険性の両面があり、リスクはゼロにはなりません。例えば、オフィス用のシュレッダーは、オフィスに子供はいない、という想定で作られていますので、子供のいる家庭に置くと子供が指を挟む、という事故が起きています。
――想定外のリスクのあることを自覚して使う必要がある。
そうなんです。外国製の製品を使う場合も、日本と外国の生活文化の違いで、想定外の事故が起こります。例えば、外国製の電気ケトルです。日本の電気ポットは、横から力が掛かっても倒れないように下
の部分を重くし、倒れても湯が50ミリリットル以上は漏れないように設定してあります。理由は、日本の場合は床や畳の上に置くこともあるので、赤ちゃんが床をはってポットにぶつかっても倒れないように、ということを想定しているからです。一方、ヨーロッパでは、ポットはテーブルの上に置くもので、床に置くことはまずありません。ところが、日本に入ってきて、床の上に置いたことが原因で赤ちゃんが大やけど、という事故が多数発生しています。
――生活文化が違うと、想定外の事が起きる、という事例ですね。
餅で窒息死する例は知られていますが、こんにゃく入りゼリーでのどをつまらせて窒息死した、という事故も、想定外の事故と言えます。私は消費者庁への報告書で、のどに詰まりやすい大きさと形を変えること、のどに詰まって取り出せないような弾力性の材質を変え、弾力性を落とすこと、それでも絶対に安全ではないから、リスクはありますよという注意書きをすること、子供と高齢者が食べると危険だからお菓子売り場で売らないこと、などを提案しました。その後、このメーカーは再発防止を徹底するため、大きさと素材を変え、のどに詰まりにくい新しい商品を発売しています。この事故の教訓は、消費者の立場では、のどに詰まる危険を知らずに食べてしまう、ということだと思います。
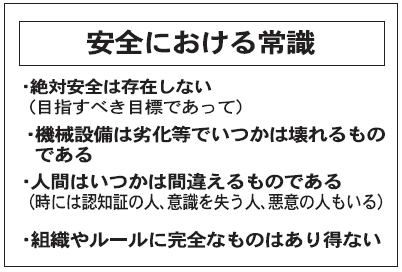

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- 1679号(2026/01/05発行)15面
- 1679号(2026/01/05発行)35面
- 1679号(2026/01/05発行)31面
- 1679号(2026/01/05発行)33面
- 1679号(2026/01/05発行)8,9面