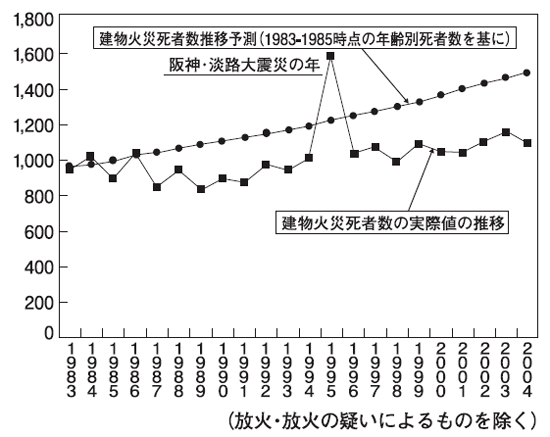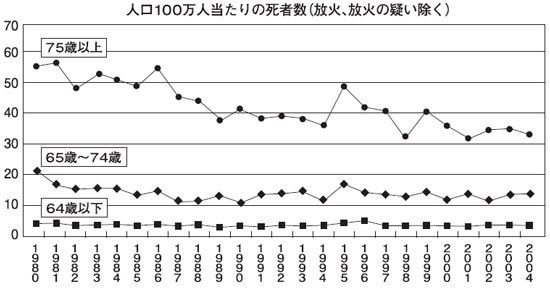東京理科大学大学院 国際火災科学研究科 関澤愛 教授
高齢化が進む日本。高齢者は、いったん火災が発生すると、とっさに消したり逃げたりするのは困難だ。住宅防火研究の第一人者である東京理科大大学院の関澤愛教授は、「高齢者は火災そのものに遭遇しないように、安全な火気器具を使ってほしい。また万が一、火災に遭っても、足腰がしっかりしていれば逃げられる」と強調。高齢者の安全と健康に配慮した防火対策を求めている。(聞き手/本紙社長・加覧光次郎)
高齢者の火災死者発生率は減少している
―――日本では近年、住宅火災による死者の約6割が65歳以上の高齢者で占められています。住宅火災が起きた場合、高齢者は若い人に比べ、亡くなるリスクが高いのでしょうか。
2009年の消防白書のデータによると、高齢者は若い人に比べ、住宅火災による死者発生リスクが高いことがデータで明らかになっています。火災による人口10万人当たりの死者数、つまり「火災による死者発生リスク」を年齢階層で分けたグラフ(図1)を見ると、71歳以降のグループからぐっと高くなります。特に81歳以上の高齢者は、70歳代の2倍近いリスクがあります。一方、40歳代以下は、火災で死ぬことはほとんどないことも分かります。中には若い方でも、寝タバコと泥酔が重なって、あるいは睡眠薬を飲み過ぎて、就寝したまま火災に遭って死亡しますが、それはまれなケースです。交通事故と違い、火災では「逃げる」というチャンスがあります。若い人は、2階の窓から飛び降りてでも、けがをしてでも、逃げる体力があるので生き延びられる。しかし、高齢者の場合、病気だったり体が不自由だったりすると、避難できずに逃げ遅れてしまいます。その点で、火災で亡くなるのは高齢者が多いというのは事実です。
【図1】火災による年齢階層別死者発生状況
―――今後、高齢者が増えると、火災で死亡する人の数も増加の一途をたどると考えられますか。
団塊世代が65歳以上になりましたので、日本では高齢者が急増しています。長寿社会となり、70代、80代の人も増えていきます。私は、高齢社会に突入する以前の1980年代に、高齢社会における火災死の問題を指摘しました。当時のデータによる火災死者発生率を基準として、1983年から2004年にかけて、建物火災による死者数がどう変化するかを予測しました。人口の高齢化に伴い、火災による死者数も年々増えていくと推測しました。
―――高齢社会における火災死の増加の問題ですね。
ところが実際には、阪神・淡路大震災のあった1995年を除いて、放火自殺を除く火災死者の実際値は1000人前後で、多少のジグザグを示しながらも横ばい状態に推移しています(図2)。その1995年を除いて、実際の値はほとんどが予測値を下回っています。2000年以降は、実際の火災死者数はやや増加傾向にありますが、予測値よりはむしろ差が開きつつあります。つまり、人口の高齢化ほど急激ではなく、もっと緩やかなペースで火災死者は増えている、というのが特徴です。
【図2】建物火災による死者数の予測値と実数値の推移
―――高齢者が増えても、社会全体の火災死は大きくは増えていないのですか。
火災死者数の増減の推移は、客観的に見るとそう言えます。また、高
齢者が火災で死亡するリスクも改善しています。1980年からの約25年間について、住宅火災による高齢者の死者発生率の推移を調べました(図3)。高齢者の年齢を、75歳以上、65~74歳、64歳以下の3つにグループ化し、火災死者発生のリスクの推移を見ました。75歳以上のリスクは最も高いのですが、この約25年間で、55・7から32・3に下がりました。65~74歳以上のグループの死者発生率も21・2から12・9へと、ほぼ半減しています。
【図3】年齢区分別に見た住宅火災による死者発生率の推移
―――そうすると、高齢者の火災対策については、従来とは違った発想が求められるのでしょうか。
私は、火災死者の数を減らすことはもちろん大事だけれど、1番大切なのは、火災発生のリスクそのものを減らすことだと考えています。これほど急激な高齢化が進んでいるのに、絶対数として減らすことは、かなりハードルが高過ぎます。火災死者数の推移をもっと客観的に見て、効果的な対策を立てる必要があると思います。

最新記事
この記事を読んでいる方は、こんな記事を読んでいます。
- 1679号(2026/01/05発行)15面
- 1679号(2026/01/05発行)35面
- 1679号(2026/01/05発行)31面
- 1679号(2026/01/05発行)33面
- 1679号(2026/01/05発行)8,9面