長く日本では顕在化してこなかった室内空気質の問題は、1995年の「シックハウス症候群」提起を頂点に一時盛り上がったものの、その後沈静化、総じて日本の住宅内空気は「清浄」になったかのようにも見える。しかし、室内空気質の問題は幅が広く、奥が深い。最新の「微生物汚染」も考えながら、今後の室内空気質の改善について考えていきたい。
化学物質汚染への注目は意外と早かった
2003年にシックハウス法が制定されたが、室内空気質住宅への国の対応はなかったと一般的には考えられている。しかし、国が化学物質による室内汚染の問題を把握していなかった、ということではない。
政府が初めて本格的に「空気」に取り組んだ法律は、1968年(昭和43年)の大気汚染防止法と言ってよいだろう(表1)。背景には、高度成長に伴い大気汚染の公害が各地で噴出し、被害に目をそむけていられなくなったことがあった。世相や社会情勢に会わせて改訂を重ね、現在に至っている。
一方、1970年には室内の空気質についての法律が施行された。「建築物衛生法」だ。これは学校や博物館のような公共の建物、大型の商業施設などを対象にした、衛生全般に関する法律で、良好な空気質の状態を保つことに大きなウェートが置かれている。この時、ホルムアルデヒドが項目にあり、相対湿度も現代に通用する基準値で設定されている。理想的な室内空気質についての理解と基準設定が40年前に行われていたのだ。
欧米諸国に目を向けると、1970年代には、後に「シックビルディング症候群」(SBS)と呼ばれることになる症状が散見されていた。
SBSは主に、目やのど・鼻への不快感から始まり、皮膚や味覚などへの障害が発生する、と定義されていた。欧米では建築物の気密化が総じて高く、室内空気質に関する規制や法律がなかった。そのためか1970〜90年代初頭まで多くの症例が報告されることになった。70年に早くも「建築物衛生法」を施行していた日本は、少なくとも公共の建物については先進的だったのだ。
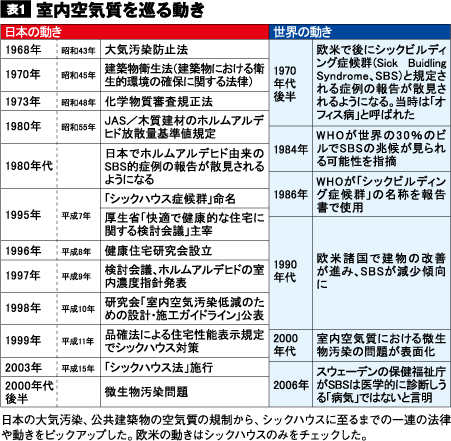
▲日本の大気汚染、公共建築物の空気質の規制から、シックハウスに至るまでの一連の法律や動きをピックアップした。欧米の動きはシックハウスのみをチェックした。
なぜ遅かった個人住宅への規制
しかし、それにもかかわらず、個人住宅への規制は遅く、後手に回った。
高度成長期には新建材が爆発的に普及して瞬く間に全国隅々にまで行き渡ったのだが、個人住宅での健康被害が表面化した時には、その数と範囲は全国的なものになっていた。「シックハウス」は早いところでは1980年代に症例の報告が始まり、1995年に「シックハウス症候群」と名づけられて、マスコミを騒がせた。
問題が顕在化した2年後にホルムアルデヒドの室内濃度の指針が公表され、以後2002年までの間に13項目の化学物質が特定され、規制された。次いで2003年の「シックハウス法」は、いわゆる建築基準の平成の大改正の際に施行されたもので、建材規制とともに、24時間換気を義務化したことに特徴がある。進む断熱化・気密化を背景に、「建材規制」「気密化」「24時間換気」の三本柱によって、住宅から「シックハウス」を駆逐する道筋をつけたのだった。
では、現在の日本の住宅ではシックハウスなど、室内空気質の問題はなくなったのだろうか。答えは残念ながら「No」だ。1つには、日本人の意識の問題がある。「換気を必要とするほどの気密は不自然」とする、旧来からの暮らしの意識はいかにも根強いのだ。そこで、シックハウスの現況とともに、新たに浮上してきた室内空気質の問題を見ていこう。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















