シックハウスは決してなくなることはないが、全体としてはかつてとは比べものにならないほど減少した。しかしそこへ新たに浮上している問題がある。「微生物汚染」だ。
快適な住環境で爆発的に増殖
新たに浮上してきたのが、微生物による空気質汚染だ。
ここでいう微生物とは、最小のものでウィルス(0.01μm〜0.1μm)、大きいものでカビなどの真菌類(1μm程度)、花粉(10μm〜)などを指す。また、サイズは格段に大きくなるがダニやダニの糞、死骸なども含まれる。
今改めてこれらの問題が急浮上したのは、化学物質放散量の減少と、気密化・断熱化によってもたらされた人間にとって快適な環境が、実はこれら微生物にとっても非常に心地よいもので爆発的に増殖するようになったためと考えられている。実に皮肉な結果と言えるだろう。
微生物汚染による障害は原因物質によって異なってくる。ウィルスの場合は、インフルエンザの発症などのように、「発病」というストレートな現象となって表れる。
花粉やダニなど、比較的サイズが大きいものの場合は、アレルギー性の疾病を引き起こす。個人差はあるが、鼻腔、気管支、喉頭ほか、主に呼吸器系を中心に、さまざまなアレルギーを発症することになる。
真菌類の場合はやや複雑になる。大体においてカビとして建材や食物など付着できる場所で繁殖するが、場合によっては肺に付着繁殖し、疾病を引き起こすこともあるので注意が必要だ。
湿度40~60%が微生物の繁殖を食い止める
こうした微生物汚染に対抗する方法は「湿度」対策しかないと考えられている。
小さいほうから見ていこう。まずウィルスだ。日本でも一般的なインフルエンザウィルスとポリオウィルスの死滅率と湿度の相関性を明らかにしたものだが、これによるとインフルエンザは相対湿度(その温度のときの飽和水蒸気量に対する空気中の水蒸気量の比率)が40~60%で死滅率が急激に高くなることが分かる。ウィルスは乾燥時に活性が高いことはよく知られている。昨年末から猛威を振るっているノロウィルスも、湿度が50%でほぼ空気感染力を失うと考えられている。
次に真菌類(カビ)を見よう。相対湿度と、カビの菌糸の伸びる速さの相関性を明らかにしたものだ。カビは高湿度下で繁殖するが、60%を割ると急激にその成長スピードを減少させる。
ではダニはどうか。ダニは高温度・高湿度の環境下で繁殖する傾向が高く、気温25度の場合は、相対湿度55%を超えると繁殖率が高くなる傾向にある。
こうしてみると、非常に都合の良いことに、湿度が40~60%程度が、ほとんどすべての微生物の繁殖を食い止めるのに最適であることが分かる。
かつて建築物衛生法で定められた「40~70%」という湿度は、当時の知見による経験的な数値だったとはいえ、近年になって最新の知見でも正しかったことが証明されたと言える。
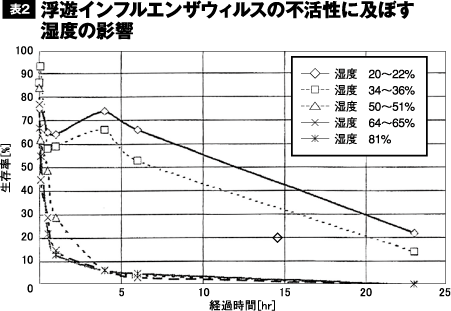
ウィルスはじめ微生物による空気質の汚染についての研究はまだ端緒についたばかりで、依然検出方法の模索も行われている状態だ。参考のため、異なるウィルスと湿度の関係を掲出した。
※出典:池田耕一「室内空気質の改善と快適空間の作り方」『快適空間創生に向けた室内空気質の改善技術』

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















