2011年の東日本大震災から、はや2年余。この間、地震についてのさまざまな論説・解説が駆け巡り、耐震はリフォーム提案の強力な柱の1つだ。4月には淡路島、宮城県、三宅島と地震が相次いだこともあり、「地震の備え」は消費者の関心を引きやすい。住宅の性能向上が目指す「構造の安定」、復旧までを含めた耐震を考える。
30年以内に震度6以上
地震の発生リスクが集中しているのは、太平洋沿岸のプレートが集まっている地点だ。今後30年以内に震度6以上の地震が起きる可能性が、60~90%以上と考えられる地域は、日本の太平洋岸の広範囲にわたっている(図2)。
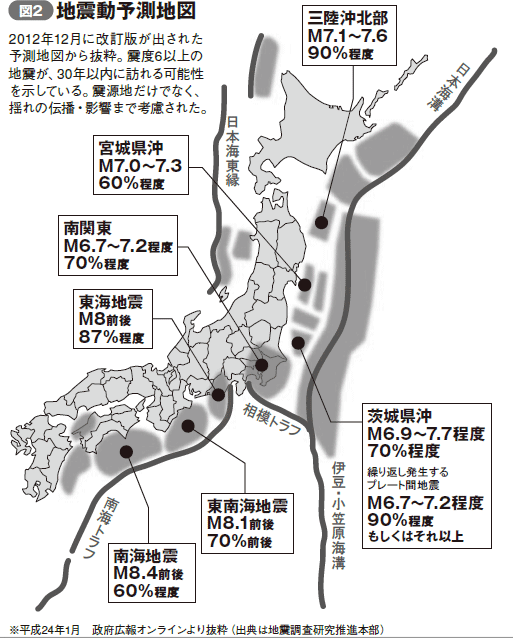
今後懸念される南海トラフ巨大地震について、被害想定は最悪220兆3千億円に上る、という有識者会議の発表も世間を騒がせた。政府は、新耐震基準に基づく住宅の耐震化率が約79%(2008年)であるのを、「2015年までに耐震化率90%」にするとしている(図3)。
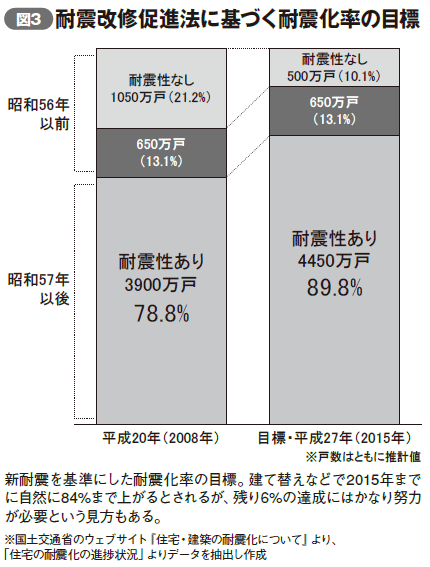
「重心」と「剛心」のズレが危険
耐震のポイントは"バランス良く"だ。例えば2階に比べて1階の耐震の程度が低いと、2階の揺れのツケが1階に回り、1階だけがつぶれるということが起きる。特に1階は窓など開口部を大きく作る傾向があるので注意が必要だ。
さらに上下のバランスだけでなく、平面でのバランスも重要だ。これは「偏心率」で表される。家には、全体の重さの中心である「重心」と、剛性の中心である「剛心」がある。その違いが偏心率で、偏心率が大きい=重心と剛心のズレが大きいと揺れの影響を受けやすくなる。専門家による構造計算をしっかり行い、バランスの良い耐震化を提案しよう。
自治体によっては耐震診断に補助金を出したり、リフォーム費用まで出すところもあるので併せて勧めたい。
余震も考えて制震を
また、「制震」も重要だ。耐震化率の高い仙台では、1度目の地震には耐えたものの、次の大きな余震で家が倒壊したという例が見られた。1度目のダメージが改善されない間に襲った余震が、ダメ押しとなったということだ。
このように余震も考えた耐震リフォームが重要になってくるが、それには現時点では「耐震」に「制震」「免震」を併用することとされる。ただ免震は技術的に難しいうえ、費用も高くつくので、揺れを吸収するダンパーなど「制震」を利用するのが良い。
「インフラ停止」に備えるリフォーム
次に、リフォームの切り口として、「インフラ停止に備える」、を提案しよう。阪神淡路大震災、東日本大震災と大きな地震を経験して分かったのは、インフラ復旧に至るまでの長い期間をしのぐのがいかに大変かということだ。
インフラ依存は都市部ほど強く、その後の生活に支障が出やすい。東北でも農村部の方が地震後の不便な状況に対して強さがあったことが分かっている。
インフラの復旧順は、電気、都市ガス、水道。埋設インフラほど復旧は遅くなる。そのため、電化率を上げるのもその後の地震の備えにはなる。ただし普段の電気代が高くなるという難点はある。
それより依存エネルギーをマルチ化したほうが良いとも言える。オール電化では、電気がストップすればすべて止まってしまうが、LPガス地域なら、LPガスも使えるようにしておけば安心できる。
エネルギーの供給源を確保するには、太陽光発電と蓄電のグレードアップも役に立つ。蓄電池はまだ開発途上で、高機能のものは依然として高価格だが一考に値する。
電気やガスにも増して、死活問題になるのは水だ。飲み水の問題はもちろん、生活用水、特にトイレにかなりの不便を強いられることになる。そこで水をコンスタントに溜める「雨水タンク」が、こうした事態にある程度有効だ。飲用には適さないが、生活用水には問題ない。水害の多い地域では助成金が付くケースもある。
地震で倒壊しない家、余震に耐える家、そして復旧までの期間を無事に過ごせる家を、リフォームで可能にする。それが「構造の安定」を高める性能向上リフォームと言えよう。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















