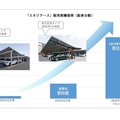「アラウーノ」 商品開発 秘話
トイレは陶器―――
そんな常識を覆したパナソニックエコソリューションズ社(大阪府門真市)の全自動おそうじトイレ「アラウーノ」。年々出荷量は増え続けており、今年度には、出荷総数が100万台を超える予定だ。開発者である酒井武之洗面トイレ商品企画チーム・チームリーダーに開発の経緯を取材した。
パナソニックエコソリューションズ社
洗面トイレ商品企画チーム
酒井武之 チームリーダー
2006年12月発売
アラウーノが発売されたのは、今から9年前、2006年12月にさかのぼる。発売当初から、有機ガラスという素材や、清掃性の高さが話題を呼んだ。ただ、実はパナソニックがトイレ事業に取り組んだのは、そこからなんと43年前、1963年のこと。土の中に埋める便槽タンクを作ったことが最初となる。1973年12月には簡易水洗便器を発売。その後、陶器製の水洗式トイレにも参入し、販売を行っていた。
当時の状況を酒井氏は「1995年に6リットルトイレを最初に出し、商品には自信がありましたが全然売れませんでした」と話す。
水洗式トイレシェアでいうとTOTO、INAXで大半を占め、後発組は検討の土台にも上がりにくい状況。さらに、陶器の生産技術で劣るパナソニックは、製品の歩留まり(良品数)が良い時でも80%、だめなときは50%と先行他社に水をあけられていた。
「陶器だからダメ」
状況を打開するきっかけとなったのは当時の役員の一言だ。「陶器でやっているからダメ、樹脂だと生産効率が上げられる」。素材を変えることで、商品の差別化もできる、との構想から2004年にプロジェクトチームが発足。新商品開発がスタートした。
開発を任された酒井氏が着目したのはお客さんニーズから導き出された清掃性だ。当時のアンケートで最も重要視される点が清掃性という結果が出ており、その点を重視した商品作りが始まった。
「そもそも、なぜ陶器のトイレが汚れるのかを調べました。段々水垢がついて表面がボコボコになってくるのです」(酒井氏)
買った当初は良く汚れが落ちるが、段々汚れが落ちにくくなった―陶器の古い便器にはよく聞かれる声だ。その原因は水垢にある。陶器の表面の釉薬と水の成分が化学結合してできた水垢が凹凸を形成。徐々に汚れが落ちにくくなる要因を作り出していた。現在は、コーティング技術の発達により、各社陶器の弱点を克服しているが、より清掃性を追求すべく、素材選びが始まった。
目を付けたのは、「撥水性」と「堅さ」を併せ持ち、水族館の水槽などにも利用されていた有機ガラスだ。細かい傷もつきにくく、素材そのものが汚れをはじく特性を持つ。そこに、パナソニック創始者の松下幸之助が洗濯機を「家庭の主婦を家事の重労働から解放する」と同じ考えの元、洗剤の泡で汚れを自動で流す「全自動お掃除トイレ」というコンセプトを付加。開発から2年後、アラウーノが誕生した。
清掃時間は2分以下
完成した便器の中はブラシ掃除する必要がほとんどなく、便座部分と便器が一体成型なので汚れがたまりにくい。実際、トイレの1回の掃除時間は、半数以上が2分以下に収まるという調査結果が出ている。
「あるお客さんからは毎日掃除をするようになったと言われました。今までのトイレだと掃除が大変だったのですが、アラウーノだとすぐできるというのです」(同氏)
男性小便の飛び散り防止にも泡が効果を発揮する。小便を忠実に再現した実証実験では、泡がクッションとなり、従来トイレよりも飛び散りを防ぐ結果となった。
発売後も、清掃性や使いやすさの追求は続く。新型からは便器の縁を約3mm立ち上げていることで、小便のもれを防ぐ「タレガード」。座った時、便座と便器の間から小便が漏れ出すのを防ぐ「モレガード」を搭載。さらに、最新商品では、洗剤を入れやすくするための専用タンクをサイドから上部に変更。また緊急時は乾電池で動く仕組みを搭載した。
最終的には「世界中の人が貧富の差に関係なく、清潔に気持ちよく用を足せるようにすること」と酒井氏。アラウーノの進化は今後も続く。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1679号(2026/01/05発行)28面
-
1679号(2026/01/05発行)27面
-
1678号(2025/12/22発行)17面
-
1679号(2026/01/05発行)28面
-
1678号(2025/12/22発行)18面