超高齢化社会において健やかな老後生活を送るには? その方法の1つが安全で住みよい自宅を形成することだ。徐々に進むバリアフリーの現状をリポートする。
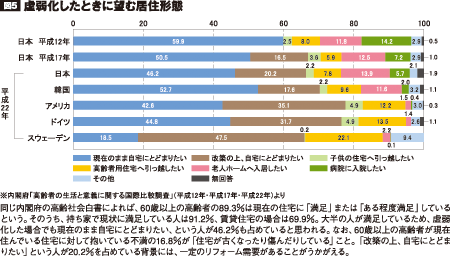
アメリカ、ドイツを上回る「自宅」こだわり
来るべき超高齢社会に向けて政府が推進している施策の1つが「安定したゆとりある住生活の確保」だ。内閣府の平成24年度版高齢社会白書では、高齢者の雇用・集合機会の確保、健康づくりの総合的推進、社会参加活動の促進などとともに、住生活の改善を挙げている。
仕事を引退した高齢者が、長い時間を過ごすのは自宅だ。日本人は特に自宅に対する執着が強い。内閣府の「平成22年高齢者の生活と意識に関する国際比較表」(図5)によれば、46.2%の高齢者が虚弱化したときに望む居住形態に「自宅」を選んでいる。これはアメリカの42.6%、ドイツの44.8%を上回る値。よりよい住環境を整えることが、よりよい老後生活につながると言っても過言ではないだろう。
数センチの段差、絨毯のめくれなどが事故原因に
だが、一方で高齢者にとって自宅は、最も事故に遭遇しやすい場所でもある。国民生活センターの「平成20年病院危害情報からみた高齢者の家庭内事故」(図6)によれば、高齢者の身に降りかかる事故の63.3%は家庭内で起こっている。そのうち居室での事故が25.8%で、階段13.1%、台所11.9%という割合(図7)だ。この数字から読み取れるのは、健常者には問題ない家でも、高齢者にとっては大きな障害が自宅に溢れているという事実だ。
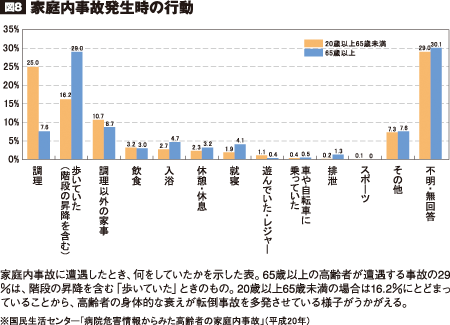
過去5年内にバリアフリーリフォーム経験アリは10%
例えば、高齢者の転倒事故の原因(図8)には床面の数センチの段差、絨毯のめくれ、通り道に横たわる電気コードなどが挙げられる。靴下をはいている場合には、階段や廊下で滑っただけで重大事故となるケースもある。心肺機能が弱った高齢者は特に日常生活での運動を控え、老化に拍車がかかるという悪循環を生みやすい。小さな転倒事故で骨折し、さらに運動を控えて寝たきりに...というケースは非常に多いのだ。皮膚が薄くなるため、わずかな火傷が重症に発展する例も少なくない。国民生活センターの報告によれば、高齢者の家庭内の死亡事故のうち、4分の3の死亡原因は火傷なのだ。
人口動態統計の「家庭内における主な不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数・構成割合」(図9)を見ても、家庭内の転倒・転落事故で亡くなった高齢者は9421人。0~64歳の死者と比較すると3倍以上で、1年間の交通事故の死者数の2倍近く(2010年交通事故死者数は4863人)にも達しているのだ。高齢者にとって自宅は決して安全な場所ではない、ということを如実に示した数字だ。
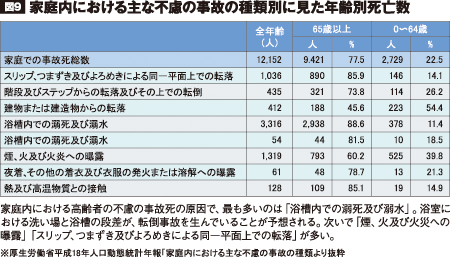
ほぼ半数の世帯が高齢者に配慮したリフォームを実施
こうした自宅での事故を減らす最善の策は、やはりバリアフリーリフォームだろう。政府も「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平成13年国土交通省告示第1301号)を打ち出し、住宅のバリアフリー化を推進。その効果は着実に出てきている。平成20年住宅・土地統計調査では「高齢者に配慮した住宅設備がある」世帯が、住宅全体の48.7%に達していると報告している(図10)。平成15年と比較すると約9ポイントも伸びているのだ。
「高齢者のための設備」で最も多くを占めているのは、手すりだ(図11)。階段に設置している住宅が1188万戸で全体の24%。次いで、浴室に設置している住宅が984万戸(19.8%)に達している。
だが、近年のバリアフリーリフォームの実施状況を見ると、不足感は否めない。過去5年以内に高齢者のための設備工事を行った世帯は全体の10%。高齢者のいる世帯で見ても、全体の15.7%にとどまっている(図12)。
高齢者のいる世帯が全体の36%を占め、その8割は一戸建てに居住し、さらにその8割以上がリフォームのハードルが高い共同住宅ではなく、持ち家に居住していてこの数字だ。バリアフリーリフォームが十分進んでいるとは言えないだろう。
この背景には高齢者の認識不足があると指摘されている。段差の解消や手すりの設置といったリフォームは、転倒事故などを未然に防ぐためのもの。転倒事故を起こしてからリフォームしても後の祭りだ。
健康でいられる間に行っておくべきなのに、現状は健康だから必要性を感じない...。こうした矛盾がバリアフリーリフォームの遅れを生んでいる。これは、国土交通省の「住生活総合調査」でも明らか。高齢期になったら、介護や住居費の負担軽減のために住み替え・改善の意向がある、と答えた人はたった7.6%しかいない。ほとんどの人が「特に考えていない」と答えているのが現状だ。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面



















