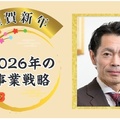自称「泥棒」だという"侵入のプロ"から聞いた「侵入しやすい家」とは?この興味深い調査をもとに"狙われやすい家"が見えてきた。
空き巣は1日約166件発生している
警視庁の調査によると、侵入窃盗の傾向では、住宅への空き巣が約44%を占めている(図1)。ここ10年来、侵入被害は減少傾向にあるが、それでも現在1日あたり全国で約166件起きている。
社会安全研究財団が、犯罪者・被疑者対象に行った興味深い統計調査がある(図2)。侵入犯つまり泥棒の自称「プロ」と「アマ」に聞いたもので、それによれば「侵入盗が最もやりやすい家」は、平屋建て、2階建ての個人宅が最上位になっている。
やりやすさ、入りやすさの判断には「逃げやすいこと」「周囲の住人の関心の低さ」が上げられた。
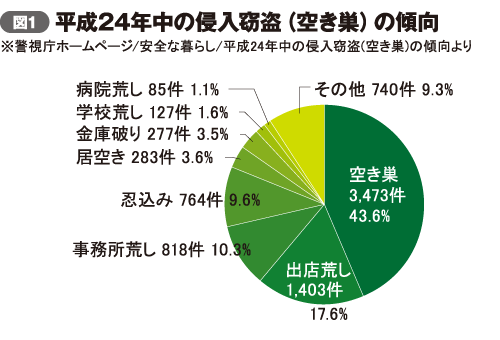
犯罪者に聞いた「やりやすい」と感じる建物。平屋建ての個人宅に集中しているように見えるが、経験値が高い犯罪者は平屋にこだわらないことに注意。

「空き巣」は、家人等が不在の住宅の屋内に侵入し、金品を盗むことをいう。「出店荒らし」は、閉店中の店舗への侵入犯をいう。
「窓から」が61%
警視庁によれば、住宅の侵入場所は、約61%が「窓」。その5割が開口部の大きく入りやすいベランダ、縁側からの侵入だ。さらに侵入者の心理として、入るまでに5分かかると約7割の者はあきらめ、10分以上かかるとほとんどあきらめるという。狙われやすい戸建て住宅の「窓」および「ドアなど開口部分」の弱点の改善と強化が防犯のポイントと言える。
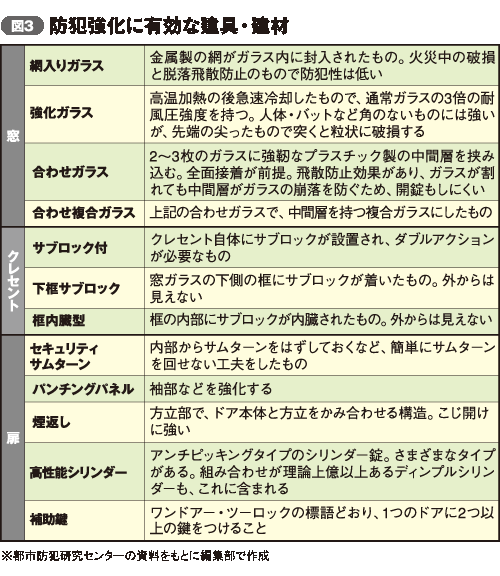
補助錠で64%が侵入を諦める
侵入手口で多いのは、クレセント錠付近のガラスを割り、手を回し入れる解錠。クレセント錠の強化、補助錠等が有効だ(図3)。窓の上下で外から見えにくい位置に付け(図4)、施錠できるシャッターや雨戸を設けるとさらに効果が高い(図5)。
さらに「防犯ガラス」にすると、バールなどの加撃物も貫通しにくくなる。2枚以上のガラスの間に柔軟で強靱な中間膜を挟んで、熱と圧力を加えて接着したもので各種ある。また防犯フィルムを貼るのも有効。打撃を加えても破れにくく、鍵をこじ開けるような大きな穴が開きにくくなる。総厚350μm以上のポリエステル製で、ガラスに全面貼りにする。
また面格子は、窓を開けたままでも防犯効果があるとされるが、ビス止めですぐはずされるようなものや、切断されるケースも多い。必ずはずされにくく、切断されにくい素材と構造になっている製品を選ぼう。
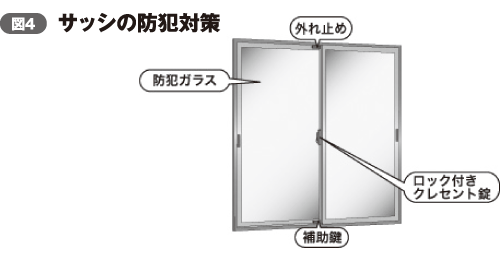
「外れ止め」で、サッシを持ち上げて外すことができないようにする。「ロック付きクレセント錠」は回転防止機能のついた強固なつくり。「補助錠」によって2ヵ所をロックすることで、容易に開くことができないようにする。
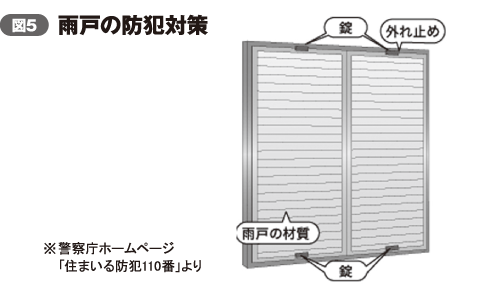
「外れ止め」で、雨戸を持ち上げて外すことができないようにする。「レールの強化」でこじ開けられにくい構造にする。「雨戸の材質」は、切り破られない材質を使うなど強度を高める。
ツーロックにシリンダー錠を
ドアの防犯はワンドア・ツーロックとし、共にシリンダー錠とするのが効果が高い。シリンダーはピッキングに強い複雑な構造で、ドリル攻撃にも耐える強固なもの。
ただし、実は侵入手口で一番多いのは「無施錠」。ゴミ出しや隣近所との行き来でついうっかり、が少なくない。せっかくの高性能の錠が無駄にならないよう、施錠の習慣づけを進言しよう。
侵入犯は、ゴミ出しルールや家の周りの整備、公園など地域マナーの状況を見て、住民の意識、周囲への関心度を確認するという。防犯設備改善の大切さと共に、不審人物を見かけたら率先して声を掛け合うなど、相互の監視・見守り、防犯意識の高さのアピールが大切である。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面