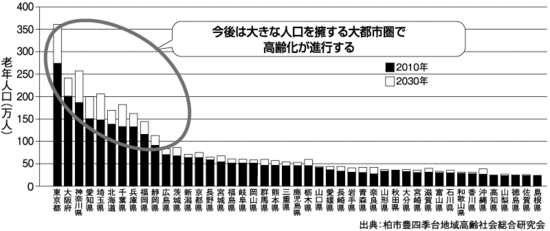在宅医療、介護、住まいの総合的支援が不可欠
医療技術の進歩の恩恵を受け、日本は誰もが長生きできる長寿社会となった。特に都市部で急速な高齢化が進み、課題も山積している。厚生労働事務次官を務め、現在は東京大学高齢社会総合研究機構で教壇に立つ辻哲夫特任教授は、「老いて体が弱っても、地域で生活者として楽しく暮らすことのできる社会システムが必要」と話す。その核となる地域包括ケアシステムと、モデルケースとして東大と千葉県柏市、UR都市機構が進めている同市の豊四季台団地での取り組みについて聞いた。 (聞き手/本紙社長・加覧光次郎)
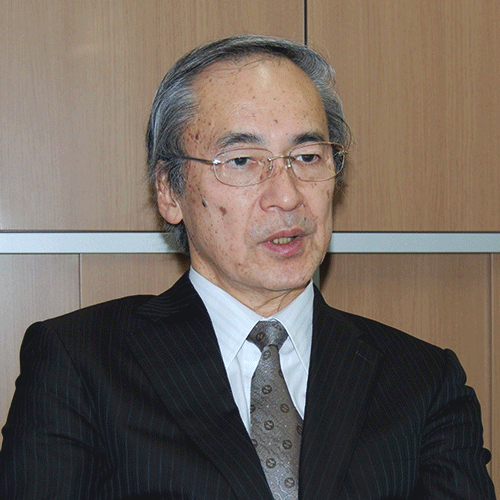 東京大学高齢社会総合研究機構 辻哲夫特任教授
東京大学高齢社会総合研究機構 辻哲夫特任教授
日本は世界でも例のない超高齢社会
―――先生は厚生労働省で長年、医療や高齢者福祉行政を担当し、医療制度改革にも携わられました。日本の高齢化の現状をどう見ておられますか。
日本は、ヨーロッパを追い越し、今は世界で高齢化の最先端を走っています。日本人の平均寿命は世界トップクラスで、人生90年社会になりました。これからのテーマは、後期高齢者の激増です。2030年には、全人口の5分の1が、75歳以上の後期高齢者で占められることが予想されています。75歳という年は、元気な方もいらっしゃいますが、一般的に言って、心身ともに衰えが見え始める年齢です。次第に老いて虚弱になっていくわけですが、その集団がこれだけ多い社会というのは、世界でもまったく例のない社会と言えると思います。
―――誰もが老いて長生きできる社会になったわけですが、高齢者が安心して暮らせるシステムの整備はこれから、というところです。
団塊世代が75歳を超える2025年が1つの節目と言われています。この時点までに、従来のシステムから超高齢社会型システムにチェンジすることが不可欠となります。
1つは、高齢者が閉じこもらない社会の仕組みづくり、もう1つは、老いて弱って亡くなっていく過程のケアシステムの充実です。長生きしても、生活者でなければ、幸せとは言えませんね。1人暮らし世帯であっても、できれば最期まで在宅で安心して過ごして老いていくシステムをつくることが必要です。
―――高齢になったら自宅に住み続け、最期も自宅で迎えたいと思うのがごく自然だと思いますが、実際には様々な理由で施設を希望する人が多いと聞きます。
今、特別養護老人ホームの待機者は50万人以上です。今は4人部屋が多いのですが、かつては6人部屋でした。この大部屋から、ユニットケアの個室に移してみました。最初は、個室にすると閉じこもって逆効果ではないかと言われていました。ところが、個室にしたら、食堂に出かけ、話をするので、歩数も会話の量も増えることが分かりました。本当に目からうろこ、でした。結局、大部屋にすると、その人らしい生活を奪うことになるのです。なるべく、自分の住み慣れた住まいに住み続けて、その人らしくその生活を繰り返すのがベストケアだということが分かりました。
―――住み慣れた環境での生活がいかに大切か、ということですね。
自分の家をベースに、その人の住まいで生活を続けていただくために、デイサービスやヘルパーを活用していただく。ただ、1人暮らしが不安な方は、見守りや食事、相談などのサービスが付いた高齢者住宅に移っていただく。その人の住まいでのライフスタイルを基本にして、在宅ケアシステムをマネジメントしていくのが、今後の日本のケア政策です。その核となるのが、「地域包括ケアシステム」です。厚生労働省は2025年に向けて、こうしたケアシステムに転換しようとしています。
―――老老介護などで悲壮に頑張るのではなく、毎日楽しく過ごして老いていくためのシステムが本当に必要ですね。
もう1つ大切なのは、在宅医療です。具合が悪くなったとき、医師が自宅に定期的に訪問してくれれば、本人も家族も安心です。実は、85歳以上の入院は怖いと言われています。救急車で病院に行って、そのまま入院。絶対安静でいると寝た切りになって、認知症も発症し、自宅に戻ることなく病院で亡くなる方が多いのです。
しかし、医師の定期訪問などがあれば、自宅で日常生活を続けることができます。病院とは違って、ペットがいてもよい。好きな食事をして、ときにはアルコールを楽しんでもよい。老いて弱っていても、自宅で生活者として暮らせる。その基本が在宅医療を含めたケアシステムだと考えています。
「地域包括ケアシステム」柏市で実現
―――先生がライフワークとして取り組んでおられる「地域包括ケアシステム」について教えてください。
「地域包括ケアシステム」とは、介護が必要になった高齢者が、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるための総合的なケア体制です。それぞれの住まいの30分圏域に、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいの5つのサービスがそろい、高齢者は自宅生活を続けながらサービスを受けられる、というイメージです。
―――東大の高齢社会総合研究機構は、URと共同で、千葉県柏市に地域包括ケアシステムのモデルをつくるプロジェクトに取り組んでいるそうですね。
千葉県柏市は都心のベッドタウンで、人口は約40万人ですが、将来、急速な高齢化が予想されています。特に高齢化が進んでいるのが、URの豊四季台団地の地域です。この団地は、URが高度経済期の1964年に開発しました。柏市全体の、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合(高齢化率)が約20%なのに対し、豊四季台団地の地域はすでに40%に達しています。大都市圏の高齢化最前線ともいえる豊四季台団地で、2025年型のシステムをつくるのが柏プロジェクトです。
―――具体的な事業内容は。
1つのポイントは、在宅医療の整備です。市内を3つのブロックに分け、医師会が中心となって、開業医を主治医、副主治医といった形でグループ化します。次に、柏市役所と医師会が連携し、在宅医療の主治医を決めます。そのコーディネート拠点となる「柏地域医療連携センター」が4月、豊四季台団地内にオープンしました。例えば、住民が「退院して、在宅生活したいけれど、訪問してくれる医師を紹介してほしい」と相談すると、柏市が窓口となって、在宅医療を含めたケアグループをセットします。
―――医師が往診してくれることになれば、安心して在宅生活を続けられます。
もう1つは、看護・介護サービスと高齢者の住まいを組み合わせた拠点の整備です。こちらはURが誘致した民間企業が、サービス付き高齢者向け住宅を5月、開設しました。1階に24時間対応型の訪問看護・介護の拠点があり、2階以上には高齢者が入居する住宅が設置されています。
24時間対応型介護サービスのビジネスは、立ち上がりのリスクが高いと言われています。利用者が少ないとすぐ赤字になってしまいます。それを、上階の高齢者に利用してもらうことで、ビジネスモデルとして安定してスタートできます。口コミで周辺の利用者が増えれば、大きな拠点をたくさんつくらなくても、自宅で頑張れる人や、大きな屋敷をシェアハウスに改造するなど、いろいろな住まい方の開発が進んで、高齢者が安心して住める地域になる、という展望です。
―――サービスが地域全体で利用されるようになれば、リフォームして自宅に住み続けたいと考える人も増えると思われます。
大切なのは、地域に住むという基本に帰ることです。在宅医療、看護、介護が安定して利用できる地域になれば、高齢になっても多様な住まい方の工夫ができます。1番いいのは、自分の住み慣れた家ですね。あるいは、古いマンションを1部改修して、そこへ住み替えることもできます。地域にはいろんな住まいがあっていい。リフォーム業界も、そういう流れに沿った動きをしていただくとありがたいですね。
元気の基は、社会に出て働くこと
―――体が弱る前に、できるだけ元気に過ごす、という意識をシニア世代が持つことも必要ですね。
そうですね。定年後に地域に帰っても、外に出るきっかけがなく、自宅に閉じこもっていると、体の機能は衰える一方です。1日1回以上外に出る人と、1週間に1回しか出ない人を比べると、認知症や歩行障害の発症リスクは、3.5倍から4倍の違いが出てきます。いかに出歩くことが大切か、よく歩き、人と接触することがいかに大切かを物語っています。結局、元気の基は「社会に出ること」です。
―――地域社会に出るための仕組みがあると、自然に足が外に向かいます。
東大は柏プロジェクトで、「生きがい就労」に取り組んでいます。リタイア層が慣れ親しんできた「仕事・就労」という形を取りつつ、セカンドライフの「生きがい」を求めるニーズに応える就労スタイルです。基本的には柏市、柏市の事業者、UR、東大が協力して、ワークシェアリングを試行しています。例えば、農園で野菜を作る、保育所で子供の見守りを担当するなど、責任ある仕事を高齢者がワークシェアし、事業者は手当を支払います。私たちは「プチ就労」と呼んでいますが、やはり就労の機会を開発していくことが大切だと思います。
高齢期を快適に住み切れる住まいに価値
――都市の高齢化が急速に進んでいます。スピードある対応が必要です。
URは、柏プロジェクトのような拠点を全国に100ヵ所くらい設置したいそうです。その次は、こういう大きな拠点ばかりに人々が移り住むというよりは、そこが在宅ケアの拠点になって、地域で多様な住まい方ができるようになるべきです。私たちの研究機構が目指している「Aging in Place(エイジング・イン・プレイス)」とは、住み慣れた地域で老いる、という意味です。これからは、高齢期を快適に住み切れる住まいと、それを支えるサービスのある地域に価値が見いだされる時代になると思います。
日本全国の高齢化の状況(都市部の状況)
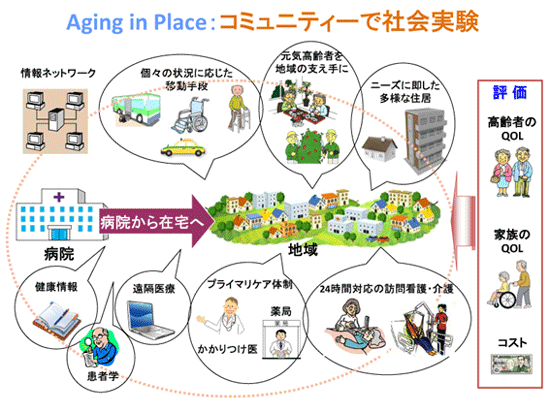
―――日本は、世界ナンバーワンの高齢社会となり、課題も切実ですが、対策も進んできています。地域包括ケアの研究は、国際的に見ても先進的な取り組みと言えるのではないでしょうか。
日本は高齢化の課題先進国ですが、国民皆保険制度と介護保険制度が整備され、全国民に医療保険や介護保険が適用されている国でもあります。日本で、地域包括ケアが国民全体に普及することに成功すれば、世界の未来に大きなメッセージを送れることになります。特に、アジアの中でも高齢化が進んでいる韓国、台湾、中国にとってのモデルになると言えます。
―――日本が大きな役割を担っているということですね。
ただ、今後は介護にかなりの財源を充てる覚悟をしないと、成功しないでしょう。今後の高齢化対策で大事なのは介護です。介護分野にかなりの財源を投入しなければ成り立ちません。
特に介護と子育て支援のために、みんなで負担をシェアして、安心して老いることのできる国をつくる。そのためにはそれなりの負担が必要という覚悟が求められています。
東京大学高齢社会総合研究機構
辻 哲夫特任教授 プロフィール
1947年兵庫県生まれ。1971年東大法学部卒業後、厚生省(当時)に入省。老人福祉課長、国民健康保険課長、大臣官房審議官(医療保険、健康政策担当)、官房長、保険局長、厚生労働事務次官等を経て、2009年4月から東大高齢社会総合研究機構教授に就任。2011年11月より現職。

最新記事
この記事を読んだ方へのおすすめ
-
1421号(2020/08/17)2面
-
1367号 (2019/07/08発行) 21面
-
1348号 (2019/02/11発行) 12面
-
1336号 (2018/11/12発行) 3面
-
1332号 (2018/10/08発行) 5面