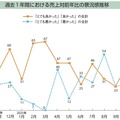第3回 ~消費税増税対応として延長保証の取り組みを~
第3回 ~消費税増税対応として延長保証の取り組みを~
消費税増税により、リフォーム価格も平成26年4月以降の引き渡し物件については、消費税増税分の値上げを原則として実施することになると思います。また、職人単価の上昇や国産材の原木価格の上昇など、原価そのものの高騰もありますから、消費増税分以上の値上げも検討しなければならないでしょう。
ところが、顧客から「便乗値上げをした」と思われてしまっては、信用失墜のリスクがあります。
この価格上昇分のフォローをどうするか?という課題があります。
価格UPをせず、増税分も含め、増税前と同一価格にするという選択は、増税分の利益を圧迫する要因になりますし、原価高騰分も利益から吸収するとなれば、リフォーム会社の経営を圧迫します。
やはり、住宅価格の引き上げは、現実として検討課題となるでしょう。ただ、値上げをする場合には、値上げをした理由について、顧客が納得できる、しっかりとした説明が必要となります。ここで出てくる観点が「値上げには、建物の性能の向上という理由があるのです」という付加価値の向上という検討課題です。性能をより向上させれば、当然、原価が上がります。他方で、原価を上げたにもかかわらず、増税分の価格転嫁を顧客に求めることができないとなると、工務店の利益が減ってしまいます。
建物のハード面の品質向上も大事ですが、私は、ソフト面の充実としての延長保証への取り組みも検討していただきたいと考えています。
例えば、これまではリフォーム工事では一律2年保証としていた住宅会社でも維持管理計画書の作成や住宅履歴情報の蓄積、リフォーム瑕疵保険の活用などにより、更なる延長保証の可能性に取り組むこともできます。これまで定期点検とクイック補修を無料奉仕で何十年と続けてきた顧客満足度の高い住宅会社にとっては、延長保証は、無料奉仕の期間を延長する取り組みに見えてしまい、抵抗感ある話に聞こえるかもしれません。
しかし、そもそもリフォームにて「2年の保証」を実施している会社であれば、2年以降、延長保証を実施するのであれば、延長保証料を受領する「保証書」を作成すればよいのです。
また、顧客との間で建物の維持管理契約を締結し、将来のリフォーム工事の予約を得ながら(10年後には断熱リフォームしましょうね、といったビジネス提案)、引き換えに定期点検時に無料補修をするような保証約款を定めることも可能です。
このように保証書や保証約款を増税のタイミングで見直し、これまで以上のサービスを提供できることをアピールすることによって、増税時の価格値上げの合理的根拠とする手法も、ご検討いただきたいと思います。

≪Profile≫日本で唯一の住宅業界を専門とする弁護士法人匠総合法律事務所の代表社員弁護士。住宅・建築紛争を数多く取り扱っている。平成13年4月に現在の弁護士法人匠総合法律事務所の前身である秋野法律事務所を開設。
| ◆秋野氏の著書◆ 『住宅会社のための消費税増税の法的リスク』 ~2冊パック~ 住宅業界の専門弁護士 秋野卓生氏が 消費税増税対策を指南! 第1弾 『住宅会社のための消費税増税の法的リスク』 消費税増税に備え住宅会社が今やるべきこととは? 第2弾 『住宅会社のための消費税増税の法的リスクII』 トラブル回避のための広告表現や営業トークの注意点を解説 【2冊セットでご注文の場合】 (1,600円 + 1,600円 = 3,200円) ⇒ 特別価格 3,000円 |
|
||||

最新記事
-
1675号(2025/12/01発行)16面
-
1675号(2025/12/01発行)16面
-
1675号(2025/12/01発行)18面
-
1674号(2025/11/24発行)25面
【連載記事一覧】
- リフォーム顧客は50〜60代 Z世代営業マンでも「昭和」の礼儀は必要
- レバーハンドル、左はオート洗浄に注意【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 【ISH2025トレンド通信】Ideal Standardと合同出展―バスルーム新提案
- 【景況感調査2025年10月】対前年比「良い」24pt増
- 【リフォーム会社のSNS活用術12】AIがSNS運用を変える プロ並みの分析を数分で実現
- 【ISHトレンド通信10】Avalegra AquaUnitなど高級水栓を一堂に展示
- 【中小企業を成長に導く20の戦略vol.3】そのまま実行するだけで中小企業を成長に導く「17の個別戦略」
- 定着前提の組織づくりの崩壊 ~キャリアステップから、キャリアチョイスの時代へ
- 【ISH2025トレンド通信09】「Escape the Ordinary」で新コレクション
- 50代管理職、若手指導に苦労 「聞かれたら」「即答」で信頼積み上げ
- ユニットバスの既設窓の大きさに注意【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 【リフォーム会社のSNS活用術11】憧れより「共感」が刺さるインフルエンサーマーケティング
- 【景況感調査2025年9月】対前年比「良い」8pt減
- 【ISH2025トレンド通信08】深化するリラクゼーション志向
- 3つの「基本戦略」が理想の組織を実現【中小企業を成長に導く20の戦略vol.2】
- 企業承継の準備は5年かかる 外部プロ人材の助けを借りて早めの準備を
- 【ISH025リアルトレンド通信07】日本発TOTOが技術力と高機能で存在感
- 【景況感調査2025年8月】売上対前年比「悪い」54%
- 浴室・ユニットバスのサイズアップ【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- リフォーム営業は商品知識だけでは通用しない 顧客の暮らしの想像力が重要
- SNS集客の未来は「AIと人間臭さの共演」がつくる【リフォーム会社のSNS活用術10】
- 仕組みで組織として発展【中小企業を成長に導く20の戦略vol.1】
- 【ISH025リアルトレンド通信06】壁掛け式便器×フレーム工法が注目
- 「採る前に分解する」人手不足時代の仕事設計
- 【ISH025リアルトレンド通信05】照明×鏡で魅せる洗面空間
- 上司は部下の「上期」「下期」「四半期」業績の振り返りを徹底しよう
- 洗面の幕板は事前に確認を【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 【景況感調査2025年7月】売上対前年比「良い」21pt増
- ショートvs長尺動画、活用すべきはどっち?【リフォーム会社のSNS活用術9】
- 【ISH2025リアルトレンド通信04】「薄い、強い、美しい」次世代洗面ボウル
- 正社員だけに頼らない組織づくりのススメ
- リフォーム検討者もAIを使う時代に、事業者はどう備えるべきか
- 洗面台の下台の高さ850mmに注意【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 【ISH2025トレンド通信03】浴びるだけで洗える〝全自動ボディケア〟
- 【景況感調査2025年6月】売上対前年比「良い」22pt減
- LINEはオープンチャットでコミュニティ育成を【リフォーム会社のSNS活用術8】
- 【ISH2025リアルトレンド通信02】PVDコーティングと炭酸水が出る水栓
- 若手に選ばれる会社になるための視点。
- 社員のモチベーションは「3つのステップ」で高まる 離職を防ぐリーダーの支援術
- 【ISH2025リアルトレンド通信】16万人強が来場 世界最大級の設備展
- 間口が狭くて洗面台が入らない?【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- Xは物語こそが共感を産み、拡散につながる【リフォーム会社のSNS活用術7】
- 【景況感調査2025年5月】売上対前年比「良い」47%
- 中小企業の将来を豊かに導く仕組みとは?【ビジョン実現型人事評価制度®連載第6回】
- 今月の数字『7』
- 「採用したい」はもう通じない?
- 「価格を下げる」だけが正解ではない。選ばれるための見積戦略とは?
- 同時給排気のレンジフードの特徴とは?【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 【景況感調査2025年4月】売上対前年比「良い」約半数
- 動画作成はつかみの5秒が生命線【リフォーム会社のSNS活用術】
- 理想の人材に成長する評価制度「5つの運用ステップ」
- 今月の数字『8』
- 若者だけじゃない。再注目されているシニア世代の人材活用
- マンションリフォーム時、ワークトップの大きさに注意を【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 社員退職は「業務見直し」のチャンスに すぐ採用せず、外注も選択肢
- 【景況感調査2025年3月】売上対前年比「良い」67%に
- TikTok、テストマーケに最適な特性を持つ【リフォーム会社のSNS活用術5】
- 社員を成長に導く「評価基準」作成のポイント【ビジョン実現型人事評価制度®連載第4回】
- ~「働きがい」と「企業成長」~人口600人の村で、正解がない未来への手探りの挑戦 おばま工務店(鹿児島県霧島市)
- 赤字社員も人不足も一挙に解決する「シェア」の力
- 今月の数字「4」【リフォーム営業活動標準化委員会】
- 防音フローリングがきっかけで訴訟問題に【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 部下を率いる方法は支配型か、サーバント型か
- 【リフォーム会社のSNS活用術4】インスタはコンセプトが命 王道はビフォーアフター
- 【景況感調査2025年2月】売上、対前年比「良い」65%
- 社員を成長に導く「経営計画」作成のポイント【ビジョン実現型人事評価制度®連載第3回】
- ~「働きがい」と「企業成長」~リフォーム業界の先頭集団へ向けた挑戦 アートリフォーム(大阪府吹田市)
- 採用戦略の根本的な見直しと制度・文化改革を
- 今月の数字「70」【リフォーム営業活動標準化委員会】
- 異音の原因は「二重トラップ」【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- リファラル採用成功のポイントは社員の協力【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 【景況感調査2025年1月】売上、対前年比「良い」29pt減
- Facebookはインスタとの連携で効率化を【リフォーム会社のSNS活用術3】
- 「ビジョン実現型人事評価制度®」がなぜ中小企業を成長に導くのか」【ビジョン実現型人事評価制度®連載第2回】
- 今月の数字『15』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 企業理念「正道を行く」 健康住宅(福岡県福岡市)
- 「社員雇用好き」の経営者がはまってしまう認知バイアス【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 築古戸建ての排水桝が落とし穴に!【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- リフォーム人材の教育は「誰を育てるか」を明確に できることを増やす、がゴール【リフォーム業務 カイゼン塾】
- YouTube、ショート動画で自社の認知拡大を【リフォーム会社のSNS活用術2】
- 【景況感調査2024年12月】売上、対前年比「良い」60%
- 「属人的経営からの脱却で稼ぐ力を劇的に向上させる仕組み」【ビジョン実現型人事評価制度®連載第1回】
- 人材難を救う切り札「内的報酬」をいかにして高めるか?【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今月の数字『30』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ MISSION_世界中の人々がワクワクできる社会を創る wakuwaku(東京都目黒区)
- お客様のパートナー的立場になろう 一緒に住まいの問題を解決【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 経験が少ない、オプション工事は、施工説明書を必ず確認!【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- ユニバーサルスペース、未経験でも即戦力 1カ月で独り立ち目指す研修
- 【景況感調査2024年11月】売上、対前年比「良い」8pt減
- 購買プロセス「AISAS(アイサス)」を知る【リフォーム会社のSNS活用術1】
- 主要5メーカーの機能まるわかり キッチン完全ガイド【今だけリフォマガ年間購読料半額】
- 今月の数字『30』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 不動産仲介件数ランキング 九州1位を目指して 明和不動産(熊本県熊本市)
- 人手不足と利益不足を解消する「ブランド力」【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 接触頻度を増やして信用を獲得 まずは人柄で勝負【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 風呂フタがないと、ある補助金がおりない?【知らなきゃ損!知るだけで避けられるトラブル事例】
- 単価1000万円以上、施主の心をつかむ大型リノベ
- 【景況感調査2024年10月】売上、対前年比「良い」半数割れ
- リフォーム売上ランキング上位は大手ばかり、中小は別の土俵で勝負を【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 優秀な30代は年収3000万円? 中小企業の人材戦略を考える【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今月の数字『3』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 「権限委譲でリーダーを育てる」鷲見製材(岐阜県岐阜市)
- 現場を支える、工事品質の要 「良い職人」と「良い関係」を築くには?
- 【景況感調査2024年9月】売上、対前年比「良い」7pt減
- 新しい取り組みは環境作りから【リフォーム業務 カイゼン塾】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 事業を通じて、日本のおじさんを元気に!HITOSUKE(東京都中央区)
- 今月の数字『14』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- 良い人材を確保するために、いま考えるべき社員の「キャリアステップ」とは【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 永森建設、2年で年間1.4億円目指すプログラム 4つのしくみで人材育成を見直し
- 【景況感調査2024年8月】売上、対前年比「良い」60%
- リフォーム事業は広告宣伝費の基準を決め、結果の検証を【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 入社2年で年間売上高6000万円、5年で1億円 新人が成長目標にすべき「理想の営業像」
- 飛びぬけた実績を持った経験者を採用したがる経営者が見落としている「落とし穴」【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今月の数字『5』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 暮らしの豊かさを求めて、カエデスタイル(福岡、神奈川)
- 滝島商店のニュースレターは営業代わり 年間1.5億につなげるコツは自己開示
- 【景況感調査2024年7月】売上、対前年比「良い」53%
- 集客成功の近道は、反響の分析から【リフォーム業務 カイゼン塾】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 誰にでも誇れる会社、仲間づくりミライホーム(愛知、東京)
- 今月の数字『60』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- 採用力と定着率を一気にアップさせる「5年ローテーションモデル」とは!?【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 山万、30歳で店長になったリーダー 絶望から学んだチームビルディング
- 【景況感調査2024年6月】売上、対前年比「良い」46%
- 集客媒体はターゲットに合わせて選ぶ【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 今月の数字『10』【リフォーム営業活動標準化委員会】
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 日本の住宅業界の常識を変える『変革者の素顔』に迫る リプライス
- 「相見積もり」対策で差 ユーザーの決め手とは?値下げはいくらまで?
- 魅力的なプロ人材を活用するなら今。プロ人材市場が熱い。【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 「今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ」【基礎から学ぶM&A 連載最終回】
- 30代の意識改革・離職減に成功 増子建築工業の評価制度とは
- 【景況感調査2024年5月】売上、対前年比「良い」22pt減
- 新人教育は2〜3カ月ごとの計画を【リフォーム業務 カイゼン塾】
- チーム・店舗での売上を最大化する 「売れる」をつくるマネジメント
- ~「働きがい」と「企業成長」~ 「ラブコール」を繰り返さない、徹底した仕組化 楓工務店
- 人材活用のプロが考える「正社員雇用すべき」人材とは【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 「今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ」【基礎から学ぶM&A 連載第7回】
- 利益を最大化するのはどっち?比較でわかる 一気通貫VS分業制
- 【景況感調査2024年4月】売上、対前年比「良い」6割超
- ~「働きがい」と「企業成長」~ ヤマタホールディングス(以下YH社)の挑戦
- ミスマッチ受注が社員の退職に【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 経営そのものをプロに任せるという選択肢がある時代【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 「今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ」【基礎から学ぶM&A 連載第6回】
- 「自分が社長だったらどうする?」甘えていた自分が、目的を持って動けるようになった 【私に刺さった上司の言葉】
- 【景況感調査2024年3月】対前年比「良い」13pt増
- 売上のベースはOB客でつくろう リピート獲得につながる満点OBフォロー
- 「リフォーム業」と「不動産業」のコラボを阻む決定的な違い【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】
- リフォーム事業者はDX推進し、価値を生む仕事に集中を【リフォーム業務 カイゼン塾】
- パッシブデザインの家【教えて善さん Vol.9】
- 社員や外部業者(弊社含む)ではなく、プロ人材に依頼すべき業務とは【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 「今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ」【基礎から学ぶM&A 連載第5回】
- 年間売上8000万円達成には"行動力"あるのみ、東栄住宅設備【エース営業インタビュー】
- 【景況感調査2024年2月】売上、対前年比「良い」26pt増
- 【私をつくる7つの習慣】 結果につながる行動の最適化
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】大手不動産会社と戦えるのか?
- 新規獲得が難しい時代、OB売上アップには「関係を細くしない」こと【リフォーム業務 カイゼン塾】
- AIクラウドHEMS【教えて善さん Vol.8】
- 「優秀な社員」を選抜した新規事業 結果は大失敗【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ【基礎から学ぶM&A 連載第4回】
- アズ建設、要望プラスαの提案力で年間売上3億円【エース営業インタビュー】
- 【景況感調査2024年1月】売上、対前年比「悪い」16pt増
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】不動産営業マンの仕事とは?
- 【高額商品を売る㊙︎テク!】 付加価値提案で満足感&差別化
- リフォーム会社の給与制度は歩合、固定?どう決める?会社や社員の成長を考え選択を【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 蓄電池とEV【教えて善さん Vol.7】
- 「大採用難」の時代、外部プロ人材を使って乗り越えるための戦略とは?【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ【基礎から学ぶM&A 連載第3回】
- アービック建設、地域密着の丁寧対応で顧客満足度アップ【エース営業インタビュー】
- 【景況感調査2023年12月】売上、対前年比「良い」17pt増
- 「不動産系FCは万能か?」【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】
- リフォーム事業の目標は社員が決める、会社は全力で支援【リフォーム業務 カイゼン塾】
- VPPってなに?【教えて善さん Vol.6】
- 無尽蔵に予算がないからこそのマーケティング戦略のポイント【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 「初めの好印象」が商談成功のカギ!これを意識するだけで変わる【初回訪問】
- 今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ【基礎から学ぶM&A 連載第2回】
- リアルキューブ、中古仲介&リノベで月1000万円【エース営業インタビュー】
- 対前年比「良い」17pt減【景況感調査2023年11月】
- いま活躍するエース営業はどのように育ったのか? 成長の軌跡でわかる!トップ営業の新人時代!
- 働き方改革は仕事の記録から 1時間単位で業務を記録しムダな仕事を削除【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 「買取再販」参入の「成功」と「失敗」【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】
- 「FIP制度」について【教えて善さん Vol.5】
- 外部のプロ人材を活用する「一歩先行く」経営スタイルとは?【ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」】
- 今リフォーム会社が知るべき、M&Aの知識とノウハウ【基礎から学ぶM&A 連載第1回】
- 【景況感調査2023年10月】売上、対前年比「良い」6pt増
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】「買取再販」実務のポイント
- 突然の「辞表」、離職防止には社員一人一人の働く動機を見極めよう【リフォーム業務 カイゼン塾】
- DRってなに?【教えて善さん Vol.4】
- ランリグ渡邉の「その仕事、正社員じゃなきゃダメですか?」Vol.1
- 【景況感調査2023年9月】売上、対前年比「悪い」7pt増
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】住宅ローンの活用による リフォーム増加の実態と課題
- リフォーム売上を達成するための部下指導は寄り添う支援【リフォーム業務 カイゼン塾】
- EV(電気自動車)とリフォーム【教えて善さん Vol.3】
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】キッチンが空間の中心。キッチンと家具をコーディネートするショールーム
- 【景況感調査2023年8月】売上、対前年比「良い」18pt減
- リフォーム会社の目標達成、PDCAのCAが重要【リフォーム業務 カイゼン塾】
- スマートハウスってなに?【教えて善さん Vol.2】
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】伸びる「新築住宅購入者」のリフォーム需要
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】オーダーキッチンを武器にした工務店経営とは?
- 【景況感調査2023年7月】売上、対前年比「良い」15pt増
- どうする?電気代!【教えて善さん Vol.1】
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】価格競争に巻き込まれない本当の「差異化」とは
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】中古住宅購入者の リフォーム事情
- リフォーム会社の業績アップは「会議」の改善から【リフォーム業務 カイゼン塾】
- 【景況感調査2023年6月】売上、対前年比「悪い」28pt増
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】不動産業参入で、収益構造はどう変わるか
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】30年間変わらない職人の賃金を1.5倍へ
- 【景況感調査2023年5月】売上、対前年比「良い」6pt減
- 【これで良いのか 長期優良住宅】自己申告だと実態把握には無理がある?
- 【これで良いのか 長期優良住宅】誰も知らない点検実績
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「多角化経営」の裏にある確かな戦略
- 【景況感調査2023年4月】売上、対前年比「良い」4pt減
- 【これで良いのか 長期優良住宅】国から届いた恐怖のお尋ね
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み7】従業員と信頼関係を築く
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】リフォーム業者が「不動産ビジネス」へ 参入する意義
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】家づくりは楽しい。アートの力で家づくりの基本に立ち返る
- 【中古住宅×リノベ最前線】物件探しを効率化するコツとは?
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】「本当に強い、住まい手に沿った家」の条件とは
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】自社PR編
- 【景況感調査2023年3月】売上、対前年比「良い」8pt減
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み6】長期的に成果を出し続けるチームワーク
- 【中古住宅×リノベ最前線】成功のための10の業務フロー
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】構造計算に取り組むと、どう変わるの?
- 【中古住宅市場とリフォーム産業の「今」と「これから」】「リフォーム業界」から 不動産業参入でワンストップ化
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】業界の垣根を取り払い、安心できる住まいの流通を
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】再生数・登録者数編
- 【景況感調査2023年2月】対前年比「良い」16pt増
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み5】アフター営業でファンづくりを
- 【中古住宅×リノベ最前線】ターゲットは新築検討者、中古リノベ3つの魅力を語ろう
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】自然検索から問い合わせ5000件 ウェブ集客の秘訣とは?
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】施主に構造の重要性を伝え、地域一番店へ
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】効果測定編
- 【景況感調査2023年1月】売上、対前年比「良い」19pt減
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み】契約率を高めるイベント戦略
- 【中古住宅×リノベ最前線】「脱価格競争」、今こそシフト
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】建築業界で働く人の離脱をなくすには
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】構造計算入門編 計算、設計・工務への生かし方
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】動画編集編
- 【景況感調査2022年12月】売上、対前年比「良い」11pt増
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み】店舗のテーマは「一点絞り」で
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】ロープアクセスを常識に。足場の組めない工事に新たな一手を
- 【リフォーム業界はTikTok集客の時代へ】インバウンド数を増やすためのプロフィールページ設計
- 【地域密着型リフォーム会社作りの設計図】人づくり・客づくり・店づくりをベースに地域密着型リフォーム会社の作り方
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】「構造計算できない」会社は、まずなにをすべき?
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】動画撮影編
- 【景況感調査2022年11月】売上、対前年比「悪い」8pt増
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み】マンパワーに頼らず売れる商流づくり
- 【リフォーム業界はTikTok集客の時代へ】TikTokの動画を魅力的にする動画編集手法
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】住宅価値の下落を防ぐ「全戸建てに維持点検と記録を」
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】これだけ変わった!住宅業界を取り巻く「構造」の法律改正
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】動画テーマ編
- 【景況感調査2022年10月】売上、対前年比「良い」26pt減
- 【半自動的に儲かる、ショールーム営業の仕組み】「ショールーム営業」とは何か
- 【リフォーム業界はTikTok集客の時代へ】最新ショート動画マーケティングを知る
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】AIの活用で住宅業界に新たな未来を
- 【地域密着型リフォーム会社作りの設計図】人づくり・客づくり・店づくりをベースに地域密着型リフォーム会社の作り方
- 【リフォーム会社の構造計算、耐震補強術】リフォーム会社や工務店が耐震、性能向上に取り組むべき理由
- 【目指せ!住宅業界の人気YouTuber】チャンネル開設にあたり準備すること
- 【景況感調査2022年9月】売上、対前年比「良い」79%
- 【リフォーム業界はTikTok集客の時代へ】利用者が急増する動画SNS「TikTok(ティックトック)」とは?
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】会社の存在意義を問い直し、業界の「売り切り」体質脱却を
- 【地域密着型リフォーム会社作りの設計図】会社の最も重要な資産でもある顧客情報を活用した戦略・戦術作り
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】リノベビジネスの肝は利益をどれだけ残せるか
- 【景況感調査2022年8月】対前年比「良い」26pt減
- 【連載 リフォーム業界のnext当たり前】「現場管理のnext当たり前」
- 【連載 強い組織づくり。今こそ新卒採用を始めよう】いい組織を継続して作るポイントとは
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】リフォームの仕事に誇りと自信を持てる人材を
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】第6回 リノベのチラシやウェブ販促、5億円企業の戦略は?
- 【地域密着型リフォーム会社作りの設計図】人づくり・客づくり・店づくりをベースに地域密着型リフォーム会社の作り方
- 【連載 リフォーム業界のnext当たり前】「ヒアリングのnext当たり前」
- 【景況感調査2022年7月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが10pt減
- 【連載 強い組織づくり。今こそ新卒採用を始めよう】採用が成功する企業の心構え
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】余剰建材を「アウトレット建材」という資源に
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】リノベならではの営業フロー、ランクアップ
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】毎月の広告宣伝費にいくら投資できるか?
- 【連載 経営者、幹部になったら確認、実践すべきこと】人事評価は「会社の形態」で決める
- 【景況感調査2022年6月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが19pt増加
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「要(かなめ)人材」を中心に組織づくりを
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】リノベーションのトレンド 断熱・耐震、今こそ差別化に乗り出すべき
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】人づくり・客づくり・店づくりをベースに地域密着型リフォーム会社の作り方
- 【連載 リフォーム経営者、幹部になったら確認、実践すべきこと】リフォーム会社の「育成・評価」
- 【連載・プロの建築写真家が教えるリフォーム施工写真の撮り方】「施工事例を上手に撮る方法」ワンポイントアドバイス
- 【景況感調査2022年5月】売上、「悪い」と感じるが対年比48%
- 【連載 強い組織づくり。今こそ新卒採用を始めよう】 求める人物像が入社したくなる組織
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】プロのインテリアをオンラインで
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】新築工務店が今こそリノベーション事業に乗り出すべき理由
- 【連載 リフォーム経営者、幹部になったら確認、実践すべきこと】「採用」は、新卒・中途で全然違う!リフォーム会社が気を付けるべき、採用の落とし穴
- 【景況感調査2022年4月】売上の対前年比は、「悪い」と感じるが20pt増
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】ファン投票第1位を目指す
- 【連載・プロの建築写真家が教えるリフォーム施工写真の撮り方】撮る前の準備
- 【連載 リフォーム業界のnext当たり前】「現地調査、見積もりのnext当たり前」
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】ホームステージングを不動産業界の「当たり前」に
- 【連載 強い組織づくり。今こそ新卒採用を始めよう】採用活動=会社のマーケティングである
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】地域密着型のリフォーム会社として揃えておきたい商売の7つ道具について
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】中小工務店だからこそ実現できた戸建リノベーション成功事例
- 【連載 リフォーム経営者、幹部になったら確認、実践すべきこと】「店長、マネジメント層の正しい時間の使い方」
- 【景況感調査2022年3月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが24pt増
- 【連載 強い組織づくり。今こそ新卒採用を始めよう】強い組織づくりのための新卒採用
- 【連載 リフォーム業界のnext当たり前】「なぜ効率化しなくてはいけないのか?」
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】不動産業界のインフラを作る
- 【連載 工務店はリフォームと新築の両輪目指せ! ビルダー向けリノベビジネスのイロハ】コダリノ研究所とは?新築工務店向けのリフォームコンサル会社です
- 【連載 リフォーム経営者、幹部になったら確認、実践すべきこと】「テクニカルスキル」と「ヒューマンスキル」
- 【景況感調査2022年2月】売上の対前年比は、「悪い」と感じるが6pt増加
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】経営理念に紐付けた戦略、戦術作り
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「デジタルプリント壁紙」でマーケット拡大を
- 【景況感調査2022年1月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが43pt減
- 「チラシ添削の個別指導塾」第4回、顧客が魅力と感じる自社の長所の考察が重要
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】商圏内におけるあなたの会社の知名度を知ると共に、ライバル会社を徹底分析し、戦略、戦術を練る
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「経営者は日本の資産。まず一度相談を」
- 【景況感調査2021年12月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが約7割
- 「チラシ添削の個別指導塾」第3回、キャッチコピー感性に訴えかけるフレーズを
- 【連載 地域密着型リフォーム会社作りの設計図】 人づくり・客づくり・店づくりをベースに地域密着型リフォーム会社の作り方
- 《連載・経営Before⇒After》リフォーム会社のDX基準を総まとめ、これからの課題をセルフチェックしよう!
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】税務のプロが見る「住宅関連企業」の課題とは...
- 【景況感調査2021年11月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが33pt増
- 「チラシ添削の個別指導塾」第2回、反響の高まる折込チラシの作り方 顧客目線で知りたい情報を適切に表現してますか?
- 《連載・経営Before⇒After》リフォーム会社のデジタルシフト、本当に成果が出た会社は「平均訪問回数」を計っていた!?
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】ユーザーの意思決定に必要な情報をオープンに
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】心地よい住まいづくりは「サスティナブル」や「ミニマル」がキーワード
- 【景況感調査2021年10月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが24pt減
- 《連載・経営Before⇒After》デジタルマーケティングで、「今リフォームしたい顧客」を見える化しよう!
- 「チラシ添削の個別指導塾」第1回、イベントチラシにはワクワクする言葉を
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】自然と顧客が集まる「インターネット商店街」
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】テクノロジーを活用して物件に「イメージ体感・共感」を
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】エスニック調が人気、空間を「彩り・調整し・区切る」ラグやカーペット
- 【景況感調査2021年9月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが22pt増
- 《連載・経営Before⇒After》実はこんなに進んでいた!?中小リフォーム会社のデジタルマーケティング
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「折り込み」か「ウェブ」か、広告戦略の課題
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】魅力的に映るベッドルームのインテリアとは
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】部屋の雰囲気を一新する照明の大きな力
- 【景況感調査2021年8月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが35pt減
- 《連載・経営Before⇒After》「中小企業デジタル化応援隊」を活用してDXの一歩を踏み出そう
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】成約率の高い顧客に出会うには?
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】家具があったほうが空間は広く見える!
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】心やすらぐアースカラーの食器を使って秋を演出
- 【景況感調査2021年7月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが68%
- 《連載・経営Before⇒After》業績向上&利益率アップに直結! 施工管理のデジタルシフト事例
- 【経営力アップ講座】今一度見直してほしい正しい定着率の高め方
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】差別化の武器になる「フローリング提案」
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】「自分の好き」と「周りの好き」は違う
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】若い女性で人気の優しげでナチュラルな韓国インテリア
- 【景況感調査2021年6月】売上の対前年比は、「良い」と感じるが59%
- 【連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】このチェンジをチャンスに
- 《連載・経営Before⇒After》リフォーム会社のための「オンライン営業」入門
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】重要なのは顧客のことを深く知る努力
- 【経営力アップ講座】顧客満足度追求のため全社の方向性を合致させる
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】物件の印象は家具の配置で決まる!
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】色や素材の体感覚を活用、「涼」を感じるインテリア
- 【連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】「N」の設計は経営方針と現状分析の掛け算で
- 【景況感調査2021年5月】売上の対前年比は、2/3が「良い」と感じる
- 《連載・経営Before⇒After》デジタル化って本当に必要?中小企業のDX成功事例と具体的な効果とは
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】工務店、リフォーム店が「家具・インテリア」を武器にするには...
- 【経営力アップ講座】未経験人材を採用・育成し活躍できる人材に
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】キッチンのリフォームを彩るインテリアアイテム
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】ついにネットで家を買う時代到来!?
- 【景況感調査2021年4月】売上の対前年比は「良い」が65%
- 【連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】重要なのは現場の営業活動との一体関係
- 《連載・経営Before⇒After》DX、ココでつまずく?!最大の関門は、システム間連携&社内浸透率
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】売り上げアップにつなげるローン会社の活用法
- 【経営力アップ講座】生産性を高めかつ定着率も高める
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】キャンプの楽しさ・非日常感をおうち空間に
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】住まい選びの未来。キーワードは「ネットで選ぶ」&「個性」
- 【景況感調査2021年3月】売上の対前年比は「良い」が53%
- 【最終回・リフォーム会社の人事戦略】人が育つ職場と離れる職場は何が違う?
- 【連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】各販促をウェブサイトとつなげてひとつにする
- 《連載・経営Before⇒After》DXに取り組む上で大切な全体設計図の作り方
- 【経営力アップ講座】1人前を明確に定義しOJTで育成する独自の取り組み
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】3月に過去最高の売り上げを出したのは...
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】お家の中でも楽しく!明るい色ニーズが増加
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】印象づくりを手伝う香りのアイテム
- 【景況感調査2021年2月】売上の対前年比は「良い」が17p増
- 【連載・リフォーム会社の人事戦略】人材確保で差がつく!リフォーム業界の採用戦略
- 【連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】ウェブ運用で活用したい法則
- 《データで考える「職人不足」》大手と中小の集客力の違いを数字で分析する
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】営業戦略会議によって契約率が変わる
- 【連載・専門家に聞く】実務経験で「建設業許可」を取得する際の注意点
- 《連載・経営Before⇒After》週休2日、残業2/3で粗利1.5倍も可能!劇的DXの設計図
- 【経営力アップ講座】健康経営を打ち出し採用に成功
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】まだまだ間に合うYouTube活用
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】「自然」感じる空間はどうつくる?
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】キーワードは「安心・安全・健康に過ごせる場所」
- 【景況感調査2021年1月】売上の対前年比は「悪い」が10p増
- 【新連載・コロナ禍中に学ぶウェブ成功法則「GANBAA」】リフォーム顧客も「世代交代」している
- 【連載・リフォーム会社の人事戦略】残業代をコントロールする営業職の給与制度
- 【連載・ロジカル経営 Vol.5】今月のテーマ、頼る技術
- 《データで考える「職人不足」》数字で見る建設業の地域差
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】お客様への連絡の決め事を作って契約率アップ
- 《新連載・経営Before⇒After》労働人口減少時代!中小企業の生存戦略
- 【経営力アップ講座】顧客宅で現場見学会 施主が良い点を説明
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「住んでから喜ばれる収納」を
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】お家の可能性「インテリアイメージ」を作る
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】天然素材で長く愛される住まいづくりを
- 【景況感調査2020年12月】売上の対前年比は「良い」が2p増
- 【連載・リフォーム会社の人事戦略】社員を戦略実行に向かわせる人事評価
- 【連載・ロジカル経営 Vol.4】今月のテーマ、パーパスオリエンテッド
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】契約後、着工までにお客様に説明するリスト
- 《データで考える「職人不足」》2021年リフォーム業界動向予測、差が開く7つのポイント
- 【経営力アップ講座】現場で実践できる安全衛生教育、現状の教育だけでは不十分!?
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】「やる気を引き出す」コーチングとは?
- 【連載・インテリアのトレンド図鑑】「色」で演出するお気に入り空間
- 【連載・住空間とインテリア Interior Recipe】「憧れのモデルルーム」から「背伸びしない等身大のインテリア」へ
- 【景況感調査2020年11月】売上の対前年比は「良い」と感じるが7pt減
- 【連載・リフォーム会社の人事戦略】行動指針で社長の考えを現場に浸透させる
- 【連載・ロジカル経営 Vol.3】今月のテーマ、研修の本質
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】最初のヒアリングフォーマットで会社評価アップ
- 《データで考える「職人不足」》工事会社を確保して「切り替え」を
- 【連載・深堀り!プロフェッショナル】業界ナンバーワンの「ポスティング」ノウハウ
- 【経営力アップ講座】若手社員が集まり、活躍する会社
- 【新連載・住空間とインテリア Interior Recipe】より住に関心が高まる中、住まい選びが変わってきた
- 【景況感調査2020年10月】売上の対前年比は「良い」と感じるが半数超
- 【連載・リフォーム会社の人事戦略】部下のモチベーションを上げて営業力UP!の3つの秘訣
- 【連載・ロジカル経営 Vol.2】今月のテーマ、新卒採用
- 《データで考える「職人不足」》「コロナ後」の工事会社経営、設備工事会社の確保が決め手
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】紹介を増やす仕組み
- 【経営力アップ講座】制度は作る事よりも、運用することが重要
- 【新連載・深堀り!プロフェッショナル】依頼率100%の秘密
- 【景況感調査2020年9月】売上の対前年比は「良い」と感じるが40%
- 【新連載・リフォーム会社の人事戦略】今こそ、生涯顧客価値を伸ばす
- 【連載・ロジカル経営】今月のテーマ、プロスピーカー
- 《データで考える「職人不足」》幅広く元請の情報を集めることが重要
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】工事中にこそしっかり説明ルールを決める
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】スタート地点は「お客様を知ること」
- 【経営力アップ講座】若手人材を採用し続ける営業会社
- 【連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】過ごす「時間」も大切に、ファニチャーセレクトのポイント
- 【景況感調査2020年8月】売上の対前年比は「良い」と感じるが22pt増加
- 《データで考える「職人不足」》災害時の「職人不足」と広域連携
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】一部でも預かってもらえるとお客様は大助かり
- 【経営力アップ講座】ICT導入は誰のため?フル活用するA社の取り組み
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】スマホの「細切れ時間」を奪う工夫を
- 【連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】4シーンから学ぶ植栽選定のコツ
- 【景況感調査2020年7月】売上の対前年比は「良い」と感じるが9pt減少
- 《データで考える「職人不足」》台風シーズンを前に考える建設会社の災害への備え
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】不動産連携にてワンストップの仕組み
- 【経営力アップ講座】「採用・教育・定着」でじっくりと人材育成を
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「変化」による新たなトレンド
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】困難なときでも安定的な商いを続けるには
- 【連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】室内と同じ安心感+解放感を得られるガーデン
- 【連載・リフォーム市場はITで切り開け!】3D建築CADソフトの導入をサポート
- 【景況感調査2020年6月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが前月調査より25pt減少
- 《データで考える「職人不足」》協力会社手配と施工管理分野のIT活用
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】OBのお客様座談会で契約率アップ
- 【経営力アップ講座】「社内大学」の設置で採用・定着率の向上を
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】変化する消費者への対応策
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】「生きた」顧客リストが危機を救う
- 【連載・リフォーム市場はITで切り開け!】コロナ時代の打ち合わせ
- 【連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】エクステリア専門スタッフの必要性を考える
- 【景況感調査2020年5月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが80%
- 《データで考える「職人不足」》コロナで改めて考える建設業経営とIT
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】廃材業者を紹介してプラスの印象を
- 【経営力アップ講座】新型コロナ禍における採用事情
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「接点獲得」と「コミュニケーション」
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】顧客との「つながり」がビジネスを強くする
- 【連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】家を楽しもう!「眺める庭から、楽しむ庭へ」
- 【連載・リフォーム市場はITで切り開け!】VRは強力な空間プレゼンツール
- 【景況感調査2020年4月】売上の対前年比は「良い」と感じるが16pt減少
- 《データで考える「職人不足」》リーマン・ショックを参考に考える、新型コロナの影響
- 【連載・住宅の大規模リフォーム】風水や税金の先生と連携すると色々お得
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】アフターコロナ時代とM&Aによる価値創造
- 【経営力アップ講座】アフターコロナを見据えたテレワーク制度の活用を
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】この変化を大きなチャンスに 必要なのは想像力
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】異常事態の中で何を売るか
- 【新連載・エクステリア&ガーデン空間提案の入門】ワンポイントオリジナル提案が心を掴む
- 【景況感調査2020年3月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが16pt増加
- 【連載・リフォーム市場はITで切り開け!】3Dで伝える古民家改修の魅力
- 《データで考える「職人不足」》新型肺炎が加速させる「職人不足」
- 【新連載・住宅の大規模リフォーム】少し損して大きく得取る
- 【経営力アップ講座】「3K」イメージを払しょくする「新3K」への変革
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】コストやパワーをどこまでかけるか
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】建設業の廃業、倒産を防ぐ方法
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】顧客との良い関係が商いを支える
- 【景況感調査2020年2月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが16pt減少
- 【連載・リフォーム市場はITで切り開け!】原状回復を武器に3Dプレゼンで切り込む
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】本当の「いい家」を提供しよう
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】個人特性に合わせた配信を
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】知り合いの社長同士のM&Aはうまくいくのか?
- 【経営力アップ講座】離職率1%台をキープする建設会社の秘訣とは
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】収益につながる仕組みを考え広告を出す
- 【景況感調査2020年1月】売上の対前年比は「良い」と感じるが7pt増
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】お客様が納得する土地の決め方
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】結果につながるコンテンツとは
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】M&Aの本質は企業価値向上
- 【経営力アップ講座】社内教育制度のPRが採用ブランディングになる
- 【新連載・リフォーム市場はITで切り開け!】スマートホームを新規開拓ツールに
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】商いの道筋を決め付加価値をうみだす
- 【景況感調査2019年12月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが11pt増
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】団信と繰上げ返済
- 【経営力アップ講座】ニーズを引き出す販売スキームで定着率アップ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】市場が落ち込む今すべきこと
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】2020年、建設業のM&Aが急増する3つの理由
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】売るべきものを見極め、人生を豊かに
- 【景況感調査2019年11月】売上の対前年比は「良い」と感じるが9pt減
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】キーワードは「コラボ」
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】固定金利のメリットを伝えよう
- 【経営力アップ講座】福利厚生とビジョンの共有で
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】大廃業時代と「外部承継」という新しい潮流
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】価値創造型の思考が新たな成果を生む
- 【景況感調査2019年10月】売上の対前年比は「良い」と感じるが29pt減
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】まずはお金に目を向けてもらおう
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】ネットの拡散力
- 【経営力アップ講座】社内プロジェクトを成功させる人材活用方法
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】2019年は売り時期か?会社売却はタイミングが重要
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】長期的な視点で動き、客を育てる
- 【景況感調査2019年9月】売上の対前年比は「良い」と感じるが6割超
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】お金の話をわかりやすく伝える
- 【経営力アップ講座】女性の活躍支援はリフォーム業界を活性
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】お客様を仲間にする
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】建設業赤字会社でも売却できる3つの理由
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】これからの企業の存続は人材にかかっている
- 【景況感調査2019年8月】売上の対前年比は「悪い」と感じるが6割
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】ヒヤリングがなぜ重要か?
- 【経営力アップ講座】予算を割かずに社員が集まる背景には地道な戦略があった
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】社員の人生に寄り添う
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】人材不足の解決策としてのスモールM&A活用法
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】今までの営みから未来の売り上げを作り出す
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド・最終回】「積極的に情報発信し、露出アップを」
- 【景況感調査2019年7月】売上の対前年比は「良い」と感じるが8pt低下
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】まずは会社と自分の説明を
- 【経営力アップ講座】ステップを明確にすると生産性・定着率がアップする
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】M&Aで事業成長を加速させる3ステップ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】リファラル採用、アプローチ前の準備
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】社員をも変える自社サービスの価値化
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】「まずはウェブサイトづくりから」
- 【景況感調査2019年6月】売上の対前年比は「良い」と感じるが12pt増加
- 【先客万来!ホームページ制作講座・最終回】ホームページとリアルな営業活動の関係とは
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】予約制イベントのすすめ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】リファラル採用、成功のための流れとポイント
- 【経営力アップ講座】内定辞退ゼロ・離職率1%台を実現する建設会社
- 【紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】「三方よし」のスモールM&A
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】顧客との絆は「質の変化」に注目する
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】美しい写真を撮るためのポイント
- 【景況感調査2019年5月】売上の対前年比は「良い」と感じるが20pt減少
- 【先客万来!ホームページ制作講座】良いホームページと悪いホームページの違いって何?
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】新人でも結果を出す仕組みとは
- 【経営力アップ講座】建設産業で女性が活躍するために
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「選ばれる」会社になる意識
- 【新連載・紙上コンサルティング 中小企業のスモールM&A活用】注目を浴びる建設業のM&A市場
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】大切なのは自社の価値を伝えること
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】事例写真はもっとも重要な情報の一つ
- 【景況感調査2019年4月】売上の対前年比は「良い」と感じるが17pt増加
- 【連載・誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】お客様への思いやりの心を持つ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】おすすめは「異業種との連携」
- 【経営力アップ講座】独自の人材育成・人材管理で生産性アップを実現
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】顧客との関係構築がレビューの鍵
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】学び・実践の繰り返しが成功を生む
- 《室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》家の中からも庭時間を楽しもう
- 【景況感調査2019年3月】売上の対前年比は「良い」と感じるが22pt減少
- 【先客万来!ホームページ制作講座】今すぐできるホームページ改善法 (1)
- 新連載スタート【誰でも敏腕セールスマンになれる!未来をつくる営業講座】分かりやすく、自社のルールで説明を
- 【経営力アップ講座】女性塗装職人3割を実現、ある建設業者の取り組み
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】全てはユーザーのため
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】「レビュー」という情報資産
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】ニーズに気づかぬ顧客に必要なものは何かを説く
- 【景況感調査2019年2月】売上の対前年比は「良い」と感じるが5割超える
- 《室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》居心地のよいバスルームからの庭
- 【先客万来!ホームページ制作講座】ホームページを正しく運用する
- 【営業マン育成講座・最終回】案件を絶対にとると決める
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年12月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】誰に、どんな理由で一番として選ばれるか
- 【経営力アップ講座】『組織は人なり』を大切にし、経営戦略をブランディングする
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】イベントには、次につなげる仕組みを持たせる
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】企業紹介にプラスαの情報を
- 【景況感調査2019年1月】売上の対前年比は「良い」と感じるが2割弱
- 【先客万来!ホームページ制作講座】更新は自分でやる?それとも頼む方がよい?
- 《室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》玄関から眺めるガーデンの提案
- 【営業マン育成講座】達成できる目標とその目的を明らかに
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年11月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「見える化」して伝え方に工夫を
- 【経営力アップ講座】現場の生産性を向上し定着率を高める
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】情熱が差別化を生む
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】最初の小さな一歩が顧客との絆を深める
- 【景況感調査2018年12月】売上の対前年比は「良い」と感じるが4割弱
- 《室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》石や植栽で和室前に風情ある景観を
- 【先客万来!ホームページ制作講座】「見られているコンテンツ」を意識する
- 【営業マン育成講座】「買う必要がない」選択肢をつぶす
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年10月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「向いている」人材の見つけ方
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】楽しさ心地よさを顧客目線で提供する
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】印象に残る企業紹介を
- 【景況感調査2018年11月】売上の対前年比は「良い」と感じるが7割超
- 【先客万来!ホームページ制作講座】10万円と300万円のホームページの違いは?
- 【使える助成金のイロハ】既存顧客にはインサイト営業できめ細やかなアフターフォローを
- 《室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》勝手口と窓の位置で提案に差をつける
- 【営業マン育成講座】どう積極的に見せるかが大事
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年9月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】コンサル会社に依頼するなら...
- 【営業力高めるVR活用】VRの技術面の進歩と今後の展望
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】自社の魅力伝える「素材」が大事
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】売るものは商品ではなくその効果である
- 【経営力アップ講座】顧客コミュニケーションがブランディングを決める
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じるが半数超
- 【使える助成金のイロハ】経営者の地盤を受け継ぐ幹部・役員の育成は急務
- 【先客万来!ホームページ制作講座】制作会社を見極めるポイント
- 《新連載・室内から見るガーデン・エクステリア空間の考え方入門》2つの窓から異なる眺めを楽しむ
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年8月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】絶対積極の境地は「無敵」
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】お客様の「見込み度」を上げていく
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】日頃から築き続けた深い絆が窮地を救う
- 【経営力アップ講座】地方発ブランドに学ぶビジネスモデル
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】オンライン上で優位に立つためには
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じるが12pt減
- 【先客万来!ホームページ制作講座】制作相談する前に準備しておく3つのこと
- 【使える助成金のイロハ】現場社員への接遇・マナー教育こそ、 競合他社に差をつけるポイントとなる
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年7月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業力高めるVR活用】360度VRコンテンツの閲覧データを活用
- 【営業マン育成講座】自らを「わたし」ではなく「わたくし」と呼ぶ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「お客様像の設定」と提供できる「価値」
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】リピーター、口コミが自然に増える秘訣とは
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じるが5pt減
- 【Houzzに学ぶブランド認知度向上ガイド】積極性と柔軟性が求められる時代に
- 【経営力アップ講座】「集める」採用活動から、「集まる」企業へ
- 【使える助成金のイロハ】全社員営業化とITツールの活用が今後の企業展望の光明となる
- 【先客万来!ホームページ制作講座】「きちんとした」ホームページが必要なわけ
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年6月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業力高めるVR活用】VRコンテンツをどのように活用するか
- 【営業マン育成講座】自己重要感が蕩(とろ)かしの根源
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「理想の顧客」を見える化
- 【経営力アップ講座】「ダイバーシティ経営」を推進し外国人労働者を取り込め
- 【事例から読み解く繁盛の方程式】今日のビジネスで、成果を導く真の秘訣とは
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じるが9pt増
- 【先客万来!ホームページ制作講座】そもそもホームページの役割とは
- 【使える助成金のイロハ】「メンタル疾患」で増える離職を防ぐには
- 【THE R STYLE】cowcamo、2018年5月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】類似が他人に影響を与える
- 【ホームステージング入門】インテリアコーディネートはトレンドを意識して
- 【営業力高めるVR活用】VR静止画コンテンツ制作用の機材とは?
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「独りよがり」になっていないか
- 新連載【事例から読み解く繁盛の方程式】心と行動の科学に基づく、ワクワク系的な営みとは
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じるが逆転
- 【経営力アップ講座】IoTとAIを活用したスマートハウスの展望
- 【使える助成金のイロハ】働き方改革関連法案が可決、同一労働同一賃金が骨子の1つに
- 【THE R STYLE】cowcamo、4月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】訊くことで人物像を多面的に見る
- 【ホームステージング入門】キッチン・水まわりはワンランク上の演出を
- 【営業力高めるVR活用】コンテンツの種類は3つ
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】優先順位の一番は...
- 【経営力アップ講座】ともに学び高め合えるビジネスパートナーとの協業を
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じる人が18pt減
- 【使える助成金のイロハ】企業全体で取り組む、業務効率化、生産性向上
- 【THE R STYLE】cowcamo、3月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】必要性の明示が成約率を左右する
- 【営業力高めるVR活用】完工後のイメージ提案に
- 【ホームステージング入門】家族の属性や価値観を見極め
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】20~30代の大きな2つの変化
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じる人が逆転
- 【経営力アップ講座】社内アカデミーによる学び方カイカクの勧め
- 【使える助成金のイロハ】長時間労働抑制のために出来る事
- 【THE R STYLE】cowcamo、2月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】雑談力は事前準備がカギとなる
- 【営業力高めるVR活用】不動産業界で先行するVR活用
- 【ホームステージング入門】ターゲットの80%が気に入る空間を
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】「求心力」のある会社
- 【景況感調査】売上の対前年比は「良い」と感じる人が8pt増加
- 【経営力アップ講座】女性社員の活躍支援で、選ばれ続ける企業へ
- 【使える助成金のイロハ】企業成長のためのコスト改善と助成金活用
- 【THE R STYLE】cowcamo、1月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 【営業マン育成講座】「自分は優秀な営業マンである」と鼓舞し自己重要感を高揚させよう
- 【連載・売れる仕組みはこう作れ!】キーワードは「憶病」「せっかち」「寂しがり」
- 【ホームステージング入門】物件購入、入って6秒で決まる
- 売上、対前年比「悪い」過半数
- 「ビジネスモデル・クオリティー」戦略キャンプで鍛える
- 就業規則の完備が企業成長の要
- 魅力的な庭を作る10のプロセス
- cowcamo、12月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 営業に必要な要素は「好きになること」
- 「スマホ」向けに対策を
- 「ホームステージング」大流行
- 売上、対前年比「悪い」が逆転
- 「労務改革」、労働環境の整備は必須
- アウトドアリビング、8つのポイント
- 「やり方が分からない」の改善が重要 ~DIY活用法~
- cowcamo、11月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 時代に即したSEO対策、最重要ポイントは...
- 売上、対前年比「良い」9pt減
- 家具のリメイク術がビジネスに ~DIY活用法~
- 内部と外部をつなぐ設計
- cowcamo、10月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 「メリットの大きいマーケティング」とは
- 売上、対前年比「良い」7pt減
- 設定やテーマを持った庭
- 濃い潜在客になる可能性が大 ~DIY活用法~
- cowcamo、9月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- それぞれ分けてアプローチを
- 売上、対前年比「良い」過半数
- 内と外をゆるやかにつなぐ「中間領域」
- 余裕のある工事日程が必要 ~DIY活用法~
- cowcamo、8月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 売上、対前年比「良い」6pt減
- 敷地全体を設計するトータルデザインの提案を
- ニーズの違いの明確化が重要 ~DIY活用法~
- cowcamo、7月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 「インバウンドマーケティング」で競合排除
- 売上、対前年比「良い」が半数
- cowcamo、6月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 売上、対前年比「悪い」が逆転
- cowcamo、5月の反響数TOP3 ~リノベーションのトレンドを探る~
- 売上、対前年比「低調」続く
- 定年退職者向けローン、毎月返済は利息のみ
- 売上、対前年比「良い」9pt悪化
- 「金利優遇リフォームローン」、エコ設備導入・耐震工事時に提案を
- 採用活動でも「マーケティング」が肝心
- 売上、対前年比2カ月連続で改善
- 各行ローンの特色プラン提案で、施主の信頼獲得
- 企業と社員の関係性の変化・求められる仕事や人材像の変化
- 売上、対前年比「良い」15pt改善
- SNSは継続的な情報発信を
- あえて建具1枚は白にしてアクセントに
- 信販系リフォームローン、「各社の特色」「付加サービス」の比較を
- 若者の働き方の多様化に対応した人材活用を
- 売上、対前年比「良い」18pt悪化
- スマホカメラ写真でブランディングを
- ダイニング空間を濃い色で引き締める
- 人材教育は、「マインド」育成で成長の継続を
- 施主の指示でも業者に責任あることも
- 金利低く、長い返済期間の「リフォーム一体型住宅ローン」
- 絞り込んだ人材へ「ダイレクトリクルーティング」
- 売上、対前年比「良い」7pt改善
- 追加工事でも契約書の作成が必須
- クロスに直塗りでシックな空間に
- 良い返事をもらえるポイントは商談プロセス
- リフォームローン、条件によっては数百万円のメリットも
- 「早期に」「逆OB訪問」「SNSで差別化」がカギ
- 売上、対前年比「良い」「悪い」が同率
- 木目模様の特殊塗装で仕上げる内装ペイント
- 「ITツールで業務効率化」は「採用力強化」に直結
- 売上、前年比「良い」25pt改善
- 「春」早期戦・「夏〜秋」中盤戦・「冬」後半戦別に戦略を
- 売上、前年比「悪い」半数に
- 一次取得者獲得のキーワードは『ライフプラン』
- 個々人が発揮できるパフォーマンスの最大化
- 「健幸リフォーム」の提案を 断熱と健康の関係
- 工事契約の代筆はダメ、法的代理人必要
- バイカラーで空間にしまりをもたらす
- 採用活動成功のカギとなる「購買行動モデル」とは
- 売上、前年比「悪い」8pt上昇
- 和室にピンクを加えてエッジを効かせる
- 目の前のパーススケッチで成約率や物件単価を向上
- 施主から修理を断られたのに雨漏り、責任は?
- FC加入でスピードアップ!成長スピードをあげよう
- Webサイト構築を行ったお客様の声
- 社員・関係者の紹介による「リファラル採用」を
- フォローは確実に!リフォームチラシ作りの極意
- 売上、前年比「悪い」12pt上昇
- 商談の場は毎回がプレゼン、基本の繰り返しが成果に
- パリのアパルトマンの雰囲気を演出
- 7月で加盟店100店突破
- 製品保証の切れが交換時期ではない
- ホームページの影響力を最大化するためのメディア運用
- 求人ポータルサイトに頼らない「ダイレクト採用」とは
- チラシの情報はなるべく絞って掲載すべき!
- 売上、前年比「悪い」10pt減
- 古びた階段をペイントで一新
- ゴールに向かい打ち合わせを着実に
- SNSトラブル、規則だけでなく教育で防止
- ターゲット・コンテンツ内容に沿ったビジュアルデザイン
- 雨漏りの原因を考える
- 雨漏り119、「雨漏りを撲滅できたら解散」
- 「求職者と接点をもつ」「入社意欲を上げる」施策とは
- 職人たちの本音...、自分たちだけの利益を考えるな
- アフター対応の中身をチラシにも
- 売上、前年比「良い」16pt改善 《リフォーム市場景況感調査》
- 天井までペイントして隠れ家のような空間に
- 顧客の要望にそったものを生産する考え方
- 完工直前で契約を解除したいと言われたら?
- 「プラン」はお客様の人生と暮らしを計画する図面
- 雨漏り解決率100%を実現
- ユーザーの興味ある情報をオリジナリティーをもって届ける
- カバー工法の留意点について
- 水まわり・小工事チラシは2カ月3回配布
- 職人たちの本音の言葉...、工期と仕事のバランスを
- 売上、前年比「良い」横ばい 《リフォーム市場景況感調査》
- 採用難時代...、住宅業界の採用戦略とは?
- スケジュールを共有してお客様をエスコート
- もしも自社の営業マンが不正をしていたら?
- 狭い空間にこそ印象的な色を提案
- 落雪の破壊力について考える 積雪地では当たり前の認識でも...
- 3つの検証から導き出された答えを軸にコンテンツを構成
- 雨漏りの根本原因解決の必要性
- PLUS ONE、奈良・三重両県で6億3000万円
- ネットで「一覧化」される企業情報の精査を
- チラシ内容で反響が高まる曜日が異なる
- 売上、前年比「良い」6pt改善 《リフォーム市場景況感調査》
- 玄関空間に温かみとニュアンスある白を
- 追加工事をする前に同意書をもらっておきましょう
- 「メモを添えて言え!」真剣さをお客様に伝える
- 検索キーワードから分かる、ユーザーの興味や関心
- 棟換気は最高の温度調節部材!
- 新築後、わずか数年で雨漏り発生
- 「見守り」「鼓舞し」「軌道修正」も。「信頼」できてから「厳しく」
- 北斗建装、大分で売上8億5000万円
- 売上、前年比「良い」14pt減で失速《リフォーム市場景況感調査》
- 薄いグリーンと白で爽やかな子供部屋に
- クレーム初期対応をマニュアル化しましょう
- 自前で職人育成するビジネスモデルの構築を
- DIYは応急処置、雨漏りには専門的な知識が必要
- どこに住んでいるどんな人に情報を届ける?
- 屋根のリフォーム、軽い屋根のはずが意外と重かった?!
- 「欲しい人材」「欲しくない人材」をはっきり打ち出す
- 山口建設、マッチングサイト軸に2ケタ成長
- 思い浮かぶ商品は文字だけでもOK、「パック」より「セット」が良い?!
- 売上、前月比「良い」が59%《リフォーム市場景況感調査》
- ニュアンスある白を生かすインテリアペイント
- ミッションロイヤリティ戦略、企業の「使命感」が成長の源
- 雨漏りで悩む想いを受け止め、真剣対応を
- 親から子世代へ、視点が広がる「住み継ぎ」リフォーム
- 何を目的にサイトを作る?背景を含めてゴールを決める
- エンラージ八王子、売上の5割が1000万円超 営業8人全員が女性
- 単純作業を奪われる「ロボット失業」時代に今すべきこと
- チラシは単なる商品掲載ダメ、コメント等で工夫を
- 売上、前年比「良い」20pt悪化《リフォーム市場景況感調査》
- 高収益を上げ続けるために、働きやすい社内システムを
- 11万でモダンな和の空間を実現
- 女子の賢い家選び、等身大の自分が「好き」に
- 雨漏り119、漏れるべくして漏れた住宅とは
- 中小企業こそWEBに強み、価格以外に判断基準を
- 現場を取り仕切る中間層に「経営視点」を持たせる方法
- アルファテック、工事中の追加依頼200件
- 塗装業界のホームページの充実・活用がカギ
- チラシ作りのポイント!難しくても工事費は定額制に
- 売上 前年比4pt改善し、好調維持《リフォーム市場 景況感調査》
- タナベ経営、「住まいと暮らし」ビジネス研究活動報告
- 反響あるチラシづくりのポイントは?メッセージは表に大きく!
- 新築マンションから一転、自然と暮らす「米軍フラットハウス」
- 雨漏り119、雨漏りに悩む人ゼロへ
- 差別化するHP戦略、セルフブランディングで「らしさ」を見つける
- イズ、顧客の75%が新規客 4つのサイトで集客を
- 若手社員を「仕事を作り出す人材」に育てるポイント
- チラシ作りのための『準備』が成否を分ける
- 職人の「独立支援制度」で未来の若者を創る
- 売上、対前年比「良い」7pt改善《リフォーム市場 景況感調査》
- 施主支給で実現した「こだわりの逸品」がある家
- Web環境の変化に対応し潜在客にアプローチ
- 雨漏り調査を変えた『赤外線カメラ』
- チラシ高反響!エリア分析する際の8つのポイントとは?
- 採用活動の短期集中は「SNSを駆使」
- 塗装店に必要なスキルとは?新規参入に立ち向かうために
- 小数派でも手堅いニーズ、単層フローリング
- 商圏調査で、1000分の1反響率をアップ
- 売上、7カ月ぶり悪化《リフォーム市場 景況感調査》
- 「マルシェ」「こども工務店」イベントで来場1327組
- 「男の料理」が生まれる、ヴィンテージキッチンとは?
- 雨漏りの調査は難解、ユーザーへ「根拠」の説明が大切
- リフォーム業界のWEB戦略、成功と失敗の違いは?
- 床材に汚れを演出する「シャビーシック」が流行
- 「結婚・出産」を組み込んだワークプランを
- 日本塗装名人社、塗装サ-ビスを維持するために
- リフォームチラシ専門会社誕生、どん底からの再起
- 住宅市場(全体) 《建材・設備マーケットデータ》
- 太陽光発電システム 《建材・設備マーケットデータ》
- 売上、前年比「良い」6カ月連続《リフォーム市場 景況感調査》
- 家庭で転倒・転落による死亡者数は7766人
- ソーラーシステム 《建材・設備マーケットデータ》
- 家庭用燃料電池(エネファーム) 《建材・設備マーケットデータ》
- いいチラシの作り方、「安くていい仕事」を訴求
- 雨漏り119、突然の雨漏り?!雨漏りの専門業者がアドバイス
- ロックウール 《建材・設備マーケットデータ》
- エコウィル《建材・設備マーケットデータ》
- 玄関ドア《建材・設備マーケットデータ》
- 人材不足を解消するには「中長期的に仕掛ける」
- 金属サイディング 《建材・設備マーケットデータ》
- リフォームを支援する海外のリモデルサイト
- 石油給湯器 《建材・設備マーケットデータ》
- グラスウール 《建材・設備マーケットデータ》
- 受注件数、前月比「悪い」29p増《リフォーム市場 景況感調査》
- アルミサッシ《建材・設備マーケットデータ》
- エコキュート《建材・設備マーケットデータ》
- ネットワーキングが"零細"をバックアップ《米国のリフォーム市場研究》
- 遮熱塗料 《建材・設備マーケットデータ》
- 米国の中古住宅売買はわかりやすく数値化 《米国のリフォーム市場研究》
- TVドアホン 《建材・設備マーケットデータ》
- "辞めない"人材を見極めるポイントは?
- ガス給湯器・ガス給湯暖房機 《建材・設備マーケットデータ》
- 浄水器 《建材・設備マーケットデータ》
- 米国の最新リフォームトレンドは?《米国のリフォーム市場研究》
- 住宅サービス業者情報へレビューを共に提供する、米リモデルサイト
- 窯業サイディング 《建材・設備マーケットデータ》
- ユニットバス 《建材・設備マーケットデータ》
- 住宅屋根用化粧スレート 《建材・設備マーケットデータ》
- 食器洗い乾燥機 《建材・設備マーケットデータ》
- 《リフォーム市場 景況感調査》 引合件数、前月比「良い」58%
- 改修ストーリーで"共感"を呼べるチラシ
- 米国の最新リフォームトレンドは?《米国のリフォーム市場研究》
- 塩ビクロス 《建材・設備マーケットデータ》
- ガス給湯器・ガス風呂給湯器 《建材・設備マーケットデータ》
- 社員個々の「夢や目標の総合計」が会社を伸ばす
- IHクッキングヒーター 《建材・設備マーケットデータ》
- 洗面化粧台 《建材・設備マーケットデータ》
- 洗練されたモダン建築を販売・紹介するサイト
- 《米国のリフォーム市場研究》 日本にないもの
- ガス給湯器 給湯専用機 《建材・設備マーケットデータ》
- ビルトインコンロ 《建材・設備マーケットデータ》
- 《リフォーム市場 景況感調査》売上、前月より「良い」52%・19p増
- 複層ガラス 《建材・設備マーケットデータ》
- 複合フローリング 《建材・設備マーケットデータ》
- 爽やかなチラシレイアウトで反響率1/5000
- 《米国のリフォーム市場研究》 日米市場の共通点
- システムキッチン 《建材・設備マーケットデータ》
- 温水洗浄便座 《建材・設備マーケットデータ》
- 多様なキッチンデザインを紹介、消費者のためのリモデルサイト
- 《米国のリフォーム市場研究》 日米市場の差異とは?
- 《リフォーム市場 景況感調査》受注件数、対前月比「変わらず」34%
- 長﨑材木店、展示場への来場月間100組呼ぶチラシとは?
- 《米国のリフォーム市場研究 第1回》 年間40兆円に迫る巨大マーケット
- 学生1人に数社の争奪戦、「1番店」になれる強み打ち出す~新卒採用の肝所~
- 《リフォーム市場 景況感調査》引合件数、前月と比べて「良い」55%
- 反響率200分の1、単価倍増のチラシ タカラ産業
- "ストレス耐性"がある学生は定着する ~新卒採用の肝所~
- 予定管理の徹底でクレーム防止しよう
- 《リフォーム市場 景況感調査》 売上、前月より「良い」63%、17pt増
- チラシで1000万円超の大型受注が倍増 安藤嘉助商店
- 断熱塗料リフォームで手軽にヒートショック防止
- 会社説明会はプレゼンの場、「入社志望」をかき立てる ~新卒採用の肝所~
- お客様目線を謙虚に受け止める ~クレーム110番~
- 《リフォーム市場 景況感調査》 売上、前月と比べ「良い」23p増
- 白黒チラシでも反響率461分の1 ~チラシづくりのコツ~
- 子育てしやすい家とは? ~HAPPYにするエコリフォーム~
- 学生をいかに惹きつけるか?中小企業の強みで勝負! ~新卒採用の肝所~
- クレームがキッカケにし、次の商談に活かす
- 消費者の心配取り除く「相談窓口」を充実したものに
- 業者選びの判断要素は「分かりやすさ」
- 《リフォーム市場 景況感調査》 引合件数、前月より「良い」32p増
- トラブルを減らすインスペクターの地位向上 ~リフォームトラブル対応策~
- 事業承継を4つの側面からアプローチ ~リフォームトラブル対応策~
- 住まいの花粉対策 ~省エネリフォーム~
- 中村工務店、イベントチラシで売上8000万円 ~チラシづくりのコツ~
- 選考作業以前に「好きになってもらう」努力を ~新卒採用の肝所~
- 出先からでもiPadで会社のパソコンを共有 ~IT活用術~
- 業界に求められるコンプライアンス ~リフォームトラブル対応策~
- 省エネ住宅ポイントを活用したOB顧客向け提案 ~リフォームトラブル対応策~
- 全員で認識を共有しクレームの予防
- 物件とリフォーム一体型ローンの注意すべき点は?
- あなたの役割は何ですか? 《成功するWEBサイトとは》
- 《リフォーム市場 景況感調査》 前月と比べ「悪い」56%
- クレームは初期対応が重要 ~リフォームトラブル対応策~
- 暖喜、イベントチラシ反響率1600分の1 ~チラシづくりのコツ~
- 自然エネルギーを活かす~省エネリフォーム~
- 過剰対応はやめ常識的な対応を ~リフォームトラブル対応策~
- 機種変更などで余ったiPhoneを防犯カメラに
- 数ミリの誤差も許さない施主様のクレーム対応は専門法律事務所と共に
- クレームになる兆候を見つける訓練を
- 自社情報の「ブレ」をなくし、イメージを統一
- 《リフォーム市場 景況感調査》利益、前月と比べ「変わらず」58%
- 内容追加やページ追加に没頭するな!《成功するWEBサイトとは》
- 豪州で人気のリノベーション番組 The Block
- 断熱リフォームの盲点~間取りと暖房
- 「黒字社員」の共通項とは?必要な人材を見極めるコツ
- 耐震提案を3Dで「視覚的」に施主に伝える
- クレーム対応は「最初のお詫び」が決め手
- サイト公開でうまくいかない場合は6カ月でリニューアル 《成功するWEBサイトとは》
- インスペクションを営業ツールに
- 《リフォーム市場 景況感調査》受注件数、前月以上に「良い」58%
- 外壁塗装で反響率3000分1のチラシ術!アイネットコープ埼玉 ~チラシづくりのコツ~
- 初の住宅購入をプロが手助け、不動産知識や手続き学ぶTV番組
- 暖かさは窓から逃げる!断熱リフォームする際の盲点
- リフォーム提案に使える非建築用アプリ
- 「中小企業で実力を試したい」「人志向」「成長志向」を獲る
- ユウマペイント 佐々木社長 → 小山塗装 小山社長
- アップリメイク 齋藤社長 → ユウマペイント 佐々木社長
- 「対応スピード」が明暗を分ける【クレーム110番】
- 中古×リフォームの効率的な契約パターンとは?
- 《リフォーム市場 景況感調査》前月調査より「良い」22pアップ
- 成約までの3つのスキームを確立する 《成功するWEBサイトとは》
- 築年数古い住宅の改修プロジェクト 歴史の街ボストン舞台に展開
- カルテット 宇野社長 → アップリメイク 齋藤社長
- リフォーる、水まわり専門で反響率3000分の1 ~チラシづくりのコツ~
- 【連載】エコリフォーム 灯をリフォームする
- 施工前と後どちらも3Dで提案し工事単価アップ サクライデンキ
- リック・プロ 井田社長 → カルテット 宇野社長
- 中小企業が優秀な若者を振り向かせるには
- さくらペイント 本田社長 → リック・プロ 井田社長
- 期待が大きいとクレームも大きい お客様目線で考え事前に防ごう 【連載】クレーム110番
- 中古住宅流通を自社内で行う場合のビジネスモデルのメリット・デメリット
- 《リフォーム市場 景況感調査》引き合い「前年並み」回答が半数
- 自社のたな卸し・見える化を再度行う 《成功するWEBサイトとは》
- ミヤケン 宮嶋社長 → さくらペイント 本田社長
- 【連載】エコリフォーム 冷蔵庫の設置場所に気を付ける
- レーザー距離計とiPadでラクラク測定
- 三輪塗装 三輪社長 → ミヤケン 宮嶋社長
- 新卒採用はスキルより「コミュニケーション力」「向上心」「責任感」
- クレーム対応...相手はどんなタイプ?!まずは冷静な対応を
- みすず 綿谷社長 → 三輪塗装 三輪社長
- イギリス2位の規模を持つ人気の不動産情報サイト Zoopla
- 《中古住宅ビジネス》不動産ビジネス、まずは経営者自ら挑戦を
- 《リフォーム市場景況感調査》 復調せず、売上悪かった55%
- 100社のうち99社が陥る"失敗するときの条件"とは? 《成功するWEBサイトとは》
- 【連載】エコリフォーム オープンキッチンとエアコンの相性
- ライズホーム 森山社長 → みすず 綿谷社長
- 「ハングリー」「前向き」な新卒を探すのはもはや〝勘違い〟
- VRゴーグルで3D空間の住宅を体感
- 空間工房 匠屋 山﨑社長 → ライズホーム 森山社長
- サイトをもう1つつくることのメリット 《成功するWEBサイトとは》
- U字溝、アンテナ、騒音をチェック 【連載】クレーム110番
- コニージャパン 小西社長 → 空間工房 匠屋 山﨑社長
- 《中古住宅ビジネス》中古流通は現場フォローの仕組みが重要
- 《リフォーム市場 景況感調査》増税後反動、予想の回復には至らず
- 「太陽光発電」市場は9800億円、236万kW
- 【連載】エコリフォーム 風通しの良い間取り
- 大工棟梁が欠陥住宅を救う、米人気番組
- 大建建設 高橋社長 → CONY JAPAN 小西社長
- 「ソーラーシステム」市場は46億円、5100台
- サンプロ 青柳社長 → 大建建設 高橋社長
- iPhoneやiPadで効率アップ!アプリ活用術3